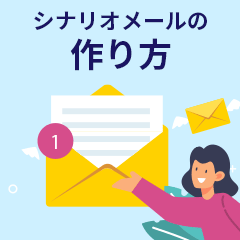アンケートで選択式の設問は奥が深い。コツと基本設計を解説
【2025年最新】企業でのBCP普及率は?対策に役立つツールも紹介!
関連製品:
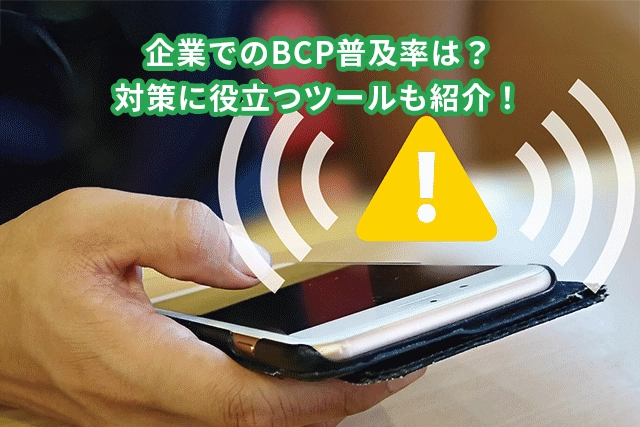
従来より台風や地震など自然災害が起きやすい日本。近年では、ゲリラ豪雨のような局所的な自然災害やサイバー攻撃や感染症など、新たな脅威も増えています。
企業にとって事業運営を維持していくこと、また早期復旧することは、顧客や従業員など非常に多くの人にとって重要です。 そこで今回はBCPについて取り上げ、その必要性や企業のBCP対策状況、役立つツールなどを紹介したいと思います。
出典:内閣府令和5年度企業の事業継続及び防災の取組に関する実態調査 (概要)
迅速・確実・簡単に安否確認を
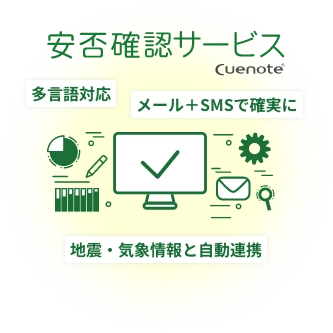
Cuenote安否確認サービスは、地震・自然災害発生時や、気象情報の発表に応じて自動通知を行い、安否確認・緊急参集が行える企業向けのサービスです。
BCPとは
BCP(Business Continuity Plan)とは事業継続計画とも呼ばれ、災害やシステム障害・サイバー攻撃や感染症などが発生した場合にも、事業を継続もしくは早期に復旧するための計画を取り決めておくことを指します。
特に日本は災害の多い国です。被災した時にも事業を適切に継続・早期に復旧することは、従業員・顧客・経営者や株主など多くのステークホルダーにとって重要です。例えば、従業員が被災して身の安全が確保できたとしても、会社が事業復旧できず倒産してしまうと、被災に加えて失職してしまう可能性もあります。また顧客もサービスを受けられず影響を受ける可能性もあります。特に被災した地域の方に提供するサービスであれば大きな影響を及ぼす可能性があります。
そのため、BCPを策定することは単なる企業の利益追求にとどまらず、社会的にも影響を与える重要なことです。
BCPの普及率は?
令和6年3月に内閣府が公表した「令和5年度企業の事業継続及び防災の取組に関する実態調査」によるとは「策定済」が大企業7割、中堅企業が5割に届かない割合でした。
令和3年度と比べ共に5ポイント程度上昇しているものの、大企業と中堅企業では対応に開きがあります。
| 大企業 | 76.4% |
|---|---|
| 中堅企業 | 45.5% |
業種別のBCP策定率
業種別のBCP策定率を見てみると、「金融・保険業」が76%程度と高い一方、「小売業」が35%程度で大きく開きがあります。また自然災害などでも早期の復旧を求められる「医療・福祉」も41%程度と課題が残る結果になっています。
| 業種 | 策定済みである | 策定中である | BCPとは何かを知らなかった |
|---|---|---|---|
| 全体 | 50.5% | 11.2% | 5.3% |
| 農業・林業・漁業 | 24.5% | 1.0% | 37.3% |
| 鉱業 | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 建設業 | 63.4% | 4.6% | 7.2% |
| 製造業 | 58.3% | 11.6% | 3.7% |
| 電気・ガス・熱供給業・水道業 | 49.8% | 15.5% | 0.0% |
| 情報通信業 | 53.8% | 12.3% | 2.6% |
| 運輸業・郵便業 | 66.2% | 6.8% | 1.1% |
| 卸売業 | 42.8% | 13.6% | 4.8% |
| 小売業 | 34.7% | 11.2% | 12.8% |
| 金融・保険業 | 76.6% | 2.6% | 1.2% |
| 不動産業・物品賃貸業 | 43.7% | 10.2% | 7.5% |
| 学術研究、専門・技術サービス業 | 50.0% | 14.8% | 2.4% |
| 宿泊業、飲食サービス業 | 27.2% | 5.4% | 13.0% |
| 生活関連サービス業、娯楽業 | 23.4% | 10.9% | 6.5% |
| 教育・学習支援業 | 18.9% | 0.0% | 12.7% |
| 医療、福祉 | 41.3% | 36.1% | 3.4% |
| 複合サービス業 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| サービス業(他に分類されないもの) | 56.7% | 13.2% | 5.9% |
BCPを策定していると得られるメリット
BCPは、被災した人が少しでも早く正常に生活できるために重要です。そして、以下の3点についてのメリット・目的もあります。
1. 経営判断
自然災害など緊急事態が発生した際にも、企業はさまざまなステークホルダーから経営判断や経営に近しい重要な判断を求められます。BCPを策定する過程においては、緊急時の権限移譲も検討する必要があります。
ケースに応じた権限移譲や、ルールに沿って従業員が行動を起こすことができれば、いかなる時においても、適切な行動を起こしやすくなります。そのため、経営者の予期せぬ長期不在などの状況においても、効果を発揮する可能性があります。
2. 機会損失
緊急時に関係者全員の安全が保たれたとしても、工場や施設・サービスが稼働しない状態の場合、機会損失が発生して企業としての存続が危ぶまれる可能性があります。
あらゆるケースにおいて、復旧する手順、また最低限復旧すべき部分などがルールとして定められていることで、影響を最小限に抑えることができます。これは災害だけでなく、部分的な機械の故障などのトラブルにおいても効果を発揮します。
3. 取引先の信用
災害を起因としたサプライチェーンの停止や納期遅れ、またはサービス提供の中止は取引先の信用へ大きく影響を与えます。災害時とは言え、「緊急時の対策を講じていない」として取引先からの信用が失われてしまう可能性もあるでしょう。このように緊急時における企業としての振る舞いは信用問題やブランディングに関わってきますので、見過ごせないポイントだと言えます。
BCP対策ツール
BCPの基本は災害などの緊急時を想定した復旧への計画・ルールの策定ですが、関連するツールも多く存在します。
- 安否確認サービス
- 備蓄品
- 災害対応チームの創設
- 避難訓練
- 火災・地震保険
この中でも近年注目されているツールが安否確認サービスです。メールやSMS・Web、アプリケーションなどの電子システムを利用して、短時間で社員の安全を確認することで、事業再開を早期に計画することができます。
安否確認サービスのメリット
実際に安否確認サービスを利用している企業からは有用性を感じています。同じく内閣府調査によると、「災害等により影響を受けた際有効であった取組」という質問に対し、「安否確認や相互連絡のための電子システ ム(含む災害用アプリ等)導入」と回答した企業は全体の37.9%、大企業に絞ると57.5%に上っています。
緊急時に最初に行うべき行動は、人の安全の確認です。そのうえで、対応できる人員などと連絡を取り、復旧に向けた行動を起こしていきます。しかし、大規模な災害の場合、ネットがつながらない・電話がつながらないなど、ケースによって可能な連絡手段が変わります。安否確認サービスでは複数の連絡手段を設けており、迅速かつ可能性高い安否確認が可能です。
おわりに
このようにBCPの策定は災害時の対応に留まらず、経営的なアドバンテージを得る上でも有用なものだとご理解いただけたと思います。
安否確認サービスなどのツール以外にも、更に組織全体として計画を考えたい場合は、内閣府が運営する「企業防災のページ」や、中小企業庁の「中小企業BCP策定運用指針」でBCP策定のガイドラインを公開していますので、ご参照ください。
緊急時でも適切に対応を行うには、事前の計画が不可欠です。不測の事態でも対処できるよう準備を万全にしておきたいものです。
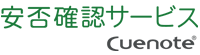 キューノート
キューノート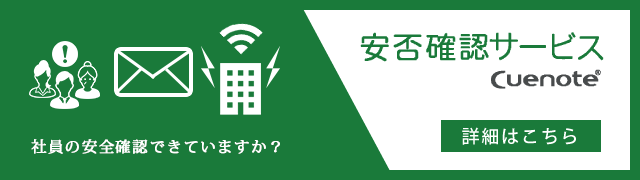
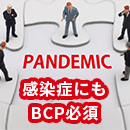 感染症にもBCP必須!初動対応は安否確認サービスが有効
感染症にもBCP必須!初動対応は安否確認サービスが有効
 企業が行う安否確認とは?目的やツールの選定方法を紹介
企業が行う安否確認とは?目的やツールの選定方法を紹介
 安否確認サービス・システムのメリットを徹底解説
安否確認サービス・システムのメリットを徹底解説