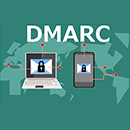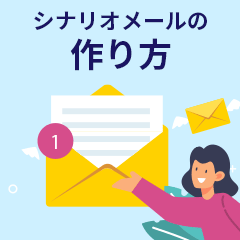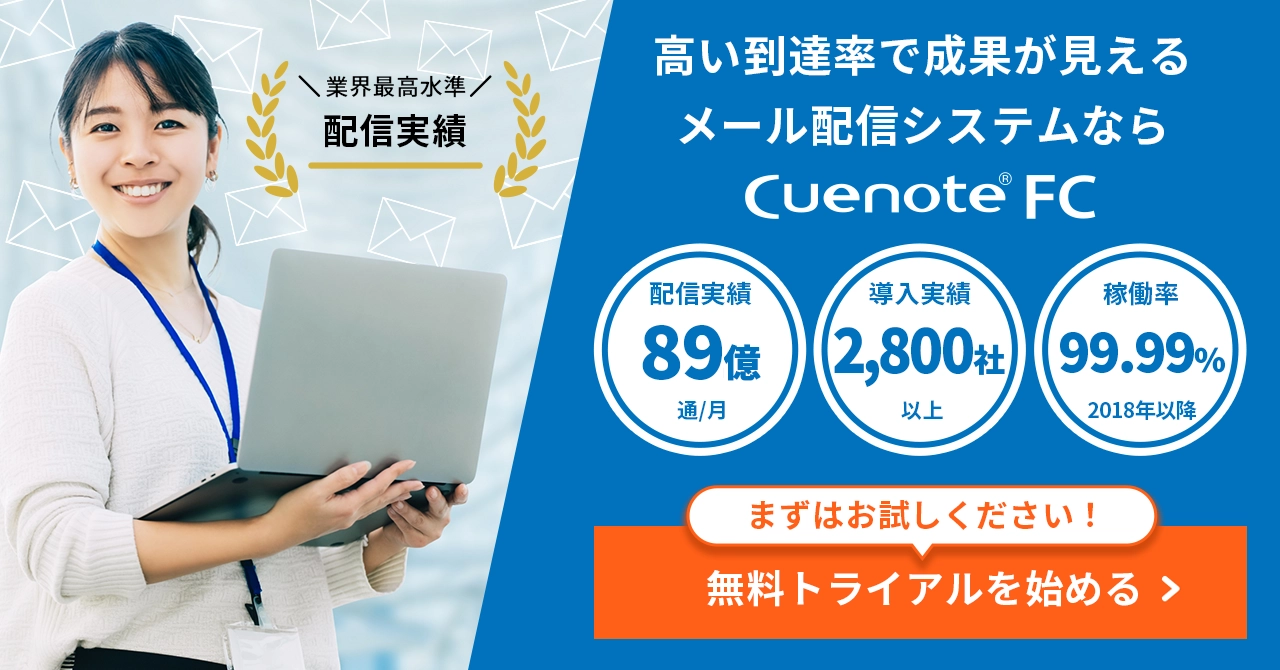SMS認証とは?仕組みやメリット・導入方法やリスクまで完全解説
マーケティングDXとは?いまさら聞けない定義や重要性を解説
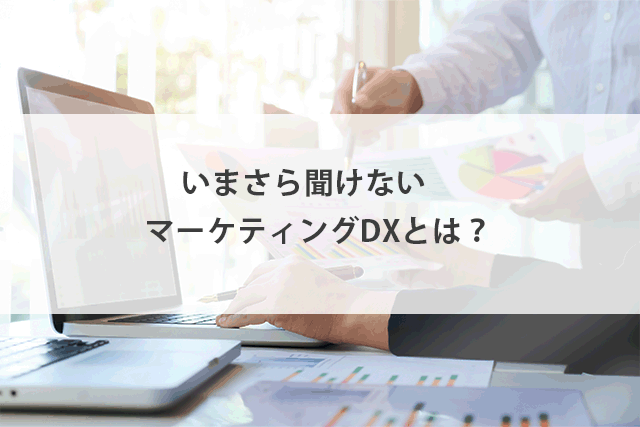
みなさんは『マーケティングDX』という言葉を聞いたことがあるでしょうか。生活様式の変化に伴って消費者の意識は大きく変化し、今やマーケティングのみならず、企業全体が『DX(デジタル変革)』の必要性に迫られています。
最近よく聞く『DX』という言葉ですが、「うまく説明できない!」「どのように進めたら良いのかわからない」という方に向けて、本コラムでは、DXの定義からそのメリット、効率よく進めていくためのきっかけなどを紹介します。
1.マーケティングDXの定義とは?
まず、DXとは『Digital Transformation』(デジタルトランスフォーメーション)の略で、日本語ではデジタルによる変革を意味します。
「trans-」はクロスするという意味で、クロスを意味する「X」が略語で使われています。
DXの定義は企業によって異なりますが、一般的に組織やビジネスのプロセスをデジタル化させるだけではなく、変革を起こすことを言います。
また、経済産業省からは、2018年12月「デジタルトランスフォーメーションを推進するためのガイドライン(DX推進ガイドライン)Ver. 1.0」が発表されており、現在もガイドラインを更新しながら、施策が推進されています。
そのガイドラインの中では、DXを下記のように定義しています。
「企業がビジネス環境の激しい変化に対応し、データとデジタル技術を活用して、顧客や社会のニーズを基に、製品やサービス、ビジネスモデルを変革するとともに、業務そのものや、組織、プロセス、企業文化・風土を変革し、競争上の優位性を確立すること」
つまりDXとは、データとデジタル技術によって商品やビジネス、業務、企業文化等の変革を成し遂げるものであり、その目的は競争力の維持・獲得・強化を果たすことにあります。
そして本コラムのテーマであるマーケティングDXは、市場調査や商品開発、広告宣伝、効果検証といったマーケティングのプロセスをITツールやAIを活用してデジタル化し、新しい価値や変革を生み出すことと定義されます。
2.『マーケティングDX』と『デジタルマーケティング』の違いは?
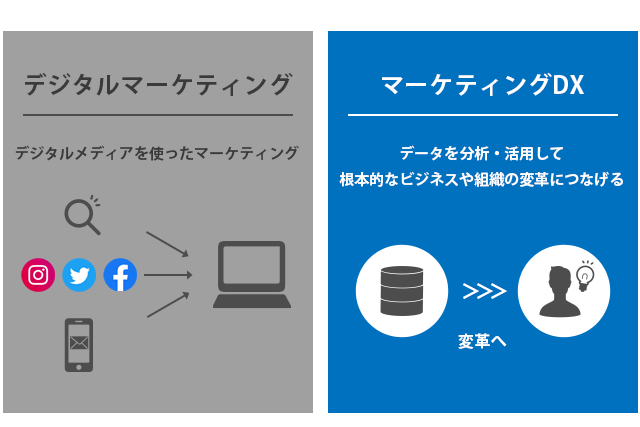
マーケティングDXと混在しやすいのが、『デジタルマーケティング』という言葉です。マーケティングに携わるみなさんは、デジタルマーケティングという言葉も耳にする機会が多いのではないでしょうか。
デジタルマーケティングとは、SNSやWebサイト、メールマガジンなど、顧客とデジタルでの接点を持つマーケティング手法のことです。
一方、マーケティングDXは先程の説明の通り、マーケティングのプロセスをITツールやAIを活用してデジタル化し、新しい価値や変革を生み出すことと定義されています。
つまり、『デジタルマーケティング』はマーケティングの手法の一つであり、『マーケティングDX』はマーケティングのプロセスそのものをデジタル化し、ビジネスや組織に変革を与えることという意味で用いるということを認識しておくのが良いでしょう。
3.マーケティングDXに期待できることとは?
次に、マーケティングDXによって期待できることは何か?という疑問について考えましょう。これは『顧客視点』と『企業視点』で分けて考えることができます。
顧客視点で期待できること
・顧客体験(CX)向上につながる
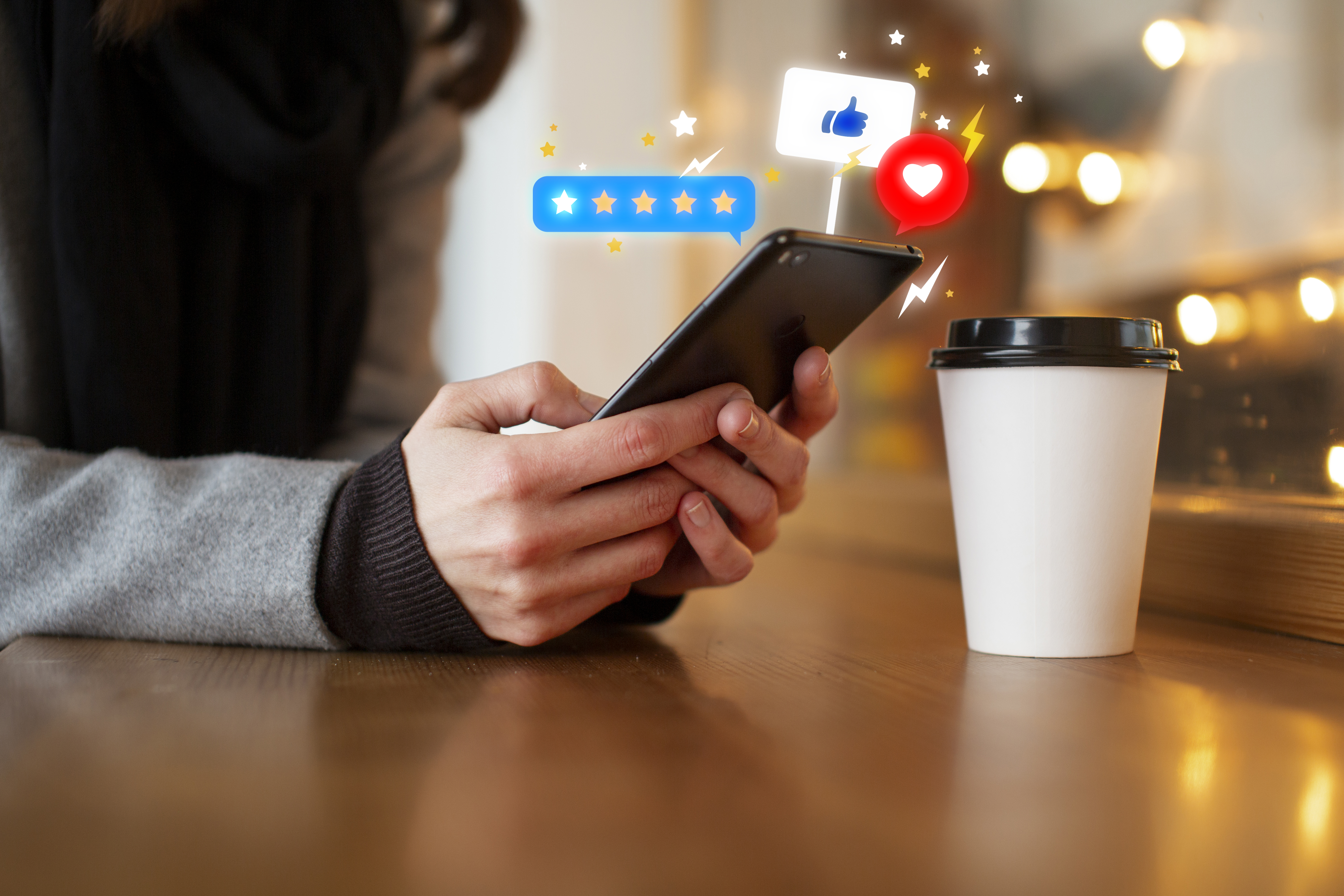
顧客視点で期待できることは、顧客体験の変革です。顧客体験はカスタマーエクスペリエンス(CX)とも呼ばれ、顧客がサービスを認知する段階から購入後のアフターサービスに至るまで、一連の体験のことを指します。
近年では「モノ消費」よりも「コト消費」が主流であると言われることもあるように、購買プロセスの中で単純に品質が高い"モノ"を所有することよりも、商品やサービスを通じて体験できる"コト"が重視されるようになってきています。
ここで重要なのが、顧客が商品やサービスに触れるあらゆる接点で満足度を上げ、ロイヤリティを高める(企業や商品に対して愛着を持ってもらう)ということです。
このような面でマーケティングDXを行うことで、顧客体験の大きな変革が期待できるようになるのです。
例えば、アプリの購買履歴に基づき、パーソナライズされた情報のみが届けられるようになると、顧客は今までよりも自分に合った快適な購買体験をできるようになります。
対面で購入できる店舗と連携して、PDCAサイクルを高速に回すことができるデジタルツールを活用することで、ユーザーニーズやトレンドの変化にあわせて柔軟にサービスをブラッシュアップすることができるため、優れた顧客体験を実現させることが可能になります。
企業視点で期待できること
・生産性が向上する
マーケティング業務では膨大なデータの収集や処理が存在し、これらは単純作業でありながら膨大な手間と時間を要します。特に、データの処理をデジタル化することで単純作業の時間が短縮され、より高度な施策に時間を使うことができます。マーケティングDXの推進に伴って、これまでの無駄な業務を改善することでコストも削減され、生産性向上にもつながるというわけです。

また、生産性向上のもう一つ理由として、データ処理のデジタル化により、PDCAサイクルを早く回せるようになることが挙げられます。マーケティング業務に限らず、どんな業務であっても、実行したら終わりというわけではありません。
一つの施策を実行したら、常に課題や改善点を見つけながら新たな戦略を立案していくことが必要です。つまり、PDCAをいかに早く回せるかが施策を成功させるカギにもなってくるのです。DXを推進し一部の作業をデジタル化することで、単純作業が短縮され、分析や施策立案の時間が確保できるようになります。
・データに基づき、定量的な判断ができるようになる
常に顧客のニーズや世の中のトレンドの変化への対応を求められるマーケティングの世界では、判断の早さが大切です。マーケティングDXに取り組むと、蓄積したデータを活用した意思決定が可能になります。
例えば、顧客とのやり取りをデータ化し、AI(人工知能)のチャットボットに学習させることができれば、従業員が対応せずとも、過去のデータに基づき顧客と最適なコミュニケーションを取ることもできるようになります。
また、施策の効果を定量的に測れるようになることもマーケティングDXを推進することのメリットになります。施策実施前後のデータを蓄積しておくことで、施策の効果があったか/無かったかの判断だけでなく、消費者の新たなニーズに気付くこともできるようになります。
・新たなサービスやビジネスモデルの構築ができる
顧客が商品やサービスを認知してから購買行動に至るまでのデータというのは、潜在的なニーズを知るための情報が集約されています。このような情報をデータとして残し、活用できている企業は多いとは言えないかもしれません。
特に企業におけるマーケティング戦略は、どうしても前例踏襲、過去の勝ちパターンに沿ったプロセスを取ってしまいがちです。そこで、新たなマーケティングプロセスや商品・サービス開発を行うための根拠となるデータが必要になります。
現在の手法で売上を伸ばしていくほか、新たな収益源を確保するためにマーケティングDXを活用するという考え方をすると良いでしょう。
マーケティングDXをテーマとした当社寄稿記事はこちらをご参照ください。
4.マーケティングDX推進のきっかけを作るためには?
「自社でもマーケティングDXを取り入れていきたいけど、なかなかきっかけがない...」という方に向けて、はじめの一歩となるような機会をいくつかご紹介します。
展示会に行く
展示会には、あらゆるジャンルのプロダクトが所狭しと並びます。定期的に開催されている大規模な展示会などに足を運ぶことで、自社の課題を解決できる意外な手段が見つかるかもしれません。
定期開催している展示会では、年間スケジュールが公開されていたりするので、計画も立てやすいかと思います。自社の課題に沿ったテーマの展示会を探してみてくださいね。
セミナー/ウェビナーに参加する
最近では、オンラインで気軽に視聴することができる「マーケティングDX」をテーマとしたセミナー/ウェビナーが多く開催されています。気になるテーマのセミナーをいくつか受けてみると、課題解決のための共通点や突破口が見つかることもあります。

デジタルツールを導入する
展示会やセミナーに参加して情報収集すると、自社の課題が明確になったり、それを解決するための手段が複数見つかってくるかと思います。自社の課題を解決する手段の糸口が見えてきた段階で、対象となるシステムやツールを提供している企業と具体的な話をするのが良いでしょう。
特にBtoB向けのサービスを提供している企業では、製品・サービスにまつわる無料セミナーを開催していることも多くあります。そのような機会を活用して、マーケティングDXに向けた一歩を踏み出してみてください。
5.まとめ
・マーケティングDXの定義
市場調査や商品開発、広告宣伝、効果検証といったマーケティングのプロセスをITツールやAIを活用してデジタル化し、新しい価値や変革を生み出すこと
・マーケティングDXによって期待できることは以下の通り
顧客視点で期待できること:顧客体験(CX)の向上・変革につながる
企業視点で期待できること:生産性が向上する/データに基づき、定量的な判断ができるようになる/新たなサービスやビジネスモデルの構築ができる
・マーケティングDXを推進するためのきっかけ
展示会に行く/セミナーやウェビナーに参加する/デジタルツールを導入する
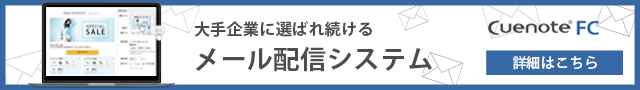
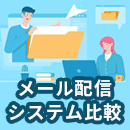 【2026年最新】メール配信システム比較17選!種類や機能・目的別選び方を徹底解説
【2026年最新】メール配信システム比較17選!種類や機能・目的別選び方を徹底解説
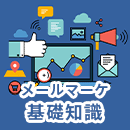 【2026年最新】メールマーケティングとは?最新調査から基礎やメリット・KPIなどを完全解説
【2026年最新】メールマーケティングとは?最新調査から基礎やメリット・KPIなどを完全解説