メールが行き違いになった際の対処法は?原因や対策を解説
感染症にもBCP必須!初動対応は安否確認サービスが有効
関連製品:

2020年代初頭に世界的に流行した『新型コロナウイルス感染症(COVID-19)』は、多くの企業や社会活動に大きな影響を及ぼしました。
工場では稼働停止、飲食店では営業休止、そして多くの企業で在宅勤務の実施など、大きな影響を受けました。今後、同規模の感染症が発生する可能性は否定できませんが、インフルエンザやノロウイルスなど、以前よりある感染症は定期的に猛威を振るっています。
このようにいつ何があるか分からない緊急時において、影響を最小限に抑え通常業務に戻るためにBCP(事業継続計画)の策定は重要です。
今回はBCPを行う際に合わせて導入したい「安否確認サービス」についても交えて解説していきます。
迅速・確実・簡単に安否確認を
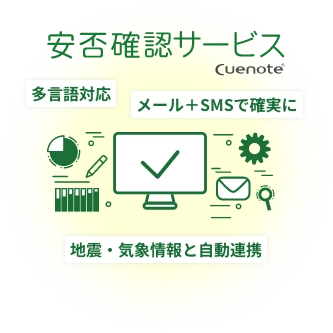
Cuenote安否確認サービスは、地震・自然災害発生時や、気象情報の発表に応じて自動通知を行い、安否確認・緊急参集が行える企業向けのサービスです。
感染症でもBCPは有効
感染症の規模や脅威のレベルによっては、一時的な事業停止を余儀なくされる可能性もあります。新型コロナウイルス感染症においては、早期に在宅勤務に変更の対応ができた企業から、時間を要したケースもあるでしょう。事業によっては1週間、1か月と事業が停止すると甚大な影響を及ぼす可能性もあります。そのため、感染症においても早期に事業復旧・継続ができるようBCPを策定していくことは非常に重要です。
自然災害と感染症におけるBCPにて検討すべき点の違い
| 観点 | 自然災害(地震・台風・洪水など) | 感染症(新型インフルエンザ・COVID-19など) |
|---|---|---|
| 発生の特徴 | 突発的・局地的に発生し、短期間で被害が集中 | 徐々に拡大し、長期化・全国的・世界的な影響 |
| 主な被害対象 | 建物・設備・インフラなどの物的資産 | 人的資源(従業員の健康・出勤制限) |
| 優先的対策対象 | 拠点・システム・物流ルートの冗長化 | 業務分担・在宅勤務体制・人員代替計画 |
| BCP発動の判断基準 | 災害発生時点(被害の有無・インフラ停止) | 感染拡大段階(感染者数・行政指示・感染率) |
| 初動対応 | 安否確認、被害状況把握、緊急避難・復旧 | 感染防止措置(マスク・検温・隔離)、在宅勤務指示 |
| サプライチェーン影響 | 局所的(特定地域の供給停止) | 広域的・長期的(国際的物流や取引先停止) |
| 想定期間 | 数日〜数週間での復旧 | 数ヶ月〜数年に及ぶ長期影響 |
自然災害と感染症においては、影響や対策すべきポイントは大きく異なります。特に感染症は、モノではなくヒトへの影響が主となり、長期的・広域的に影響を及ぼします。
BCP対策も、自然災害は対応可能なメンバーを募って早期の復旧を目指すことに対して、感染症では感染拡大を抑えながら事業継続を行う必要があります。
特に介護施設など、感染症で重症化が危惧される方が利用するサービスにおいては、事業継続の必要性と継続によるリスクの両面を踏まえて都度判断することが求められます。
感染症においてBCP策定することのメリットとは
さて、そもそもBCP策定することで、企業にどのようなメリットがあるのでしょうか?
- 事業の継続
- 操業度の回復
- 企業の信用・イメージの向上
- 終息後のビジネス競争で優位に立てる
「事業の継続」と「操業度の回復」はBCPで本来目的としているメリットです。緊急時でも事業が継続できる最低限の操業レベルに回復・維持するべく、計画を策定します。
一方で「企業の信頼性・イメージの向上」「終息後のビジネス競争で優位に立てる」というのは副次的な効果です。緊急時でも事業継続することで、関係各社から「安全で責任感のある企業」という印象を持たれるでしょう。結果的に企業の信用やイメージ向上に繋がり、CSR的な側面でのメリットが得られます。
感染症BCPにおいては、事前の準備が重要
自然災害においても事前の準備が必要ですが、機材や建物の故障はなく人だけの要因で事業継続が困難になる感染症においては、より事前準備が必要です。
人員確保と代替要員や権限移譲
感染症の場合、誰がいつ発症し、業務が困難になるか分かりません。人が足りなくなった時に異なる部署や外部など、あらゆる手段で確保ができる準備は必要です。また、代替要員が見つからない場合でも、権限を移譲するなどして適切に事業が継続できるように準備する必要があります。
これは、大規模感染症だけでなく、社員の産休や長期休職・重要な場面での出勤ができない事態などが発生した時、また突然の退職などにも役立つことができます。
テレワーク・リモート対応体制の整備
新型コロナウイルスの流行後、多くの企業で出社体制を再構築する動きが見られました。しかし、今後同様の規模が発生する可能性は0ではなく、BCPの観点からすれば、いつでもテレワークを実施できる体制の準備はしておいたほうが良いでしょう。
台風や雪など交通網が一時的に機能しなくなる場合においても、テレワークに切り替えられることは、リスクヘッジにもなるでしょう。
日ごろからの感染防止対策の徹底
大規模感染症でなくとも、インフルエンザやノロウイルスなどさまざまな感染症はあります。アルコール消毒や手洗い、消毒、咳が出ているときのマスク着用など、いわゆる「風邪予防」は、日ごろから徹底できるよう社内環境を整えておくことは重要です。
災害規模の感染症が起きた場合は、安否確認も有効
安否確認サービスは、感染症におけるBCP対策においても効果的です。簡単・迅速に社員への情報を伝えられ、安否や施設の稼働状況、業務遂行の可否など、受信者からの回答も得られます。円滑に現状把握ができ、次のアクションプランへ早期に繋げることができます。
新型インフルエンザ流行時でも活躍
活用方法として参考になるのが2009年に世界的に流行したH1N1型インフルエンザ(いわゆる新型インフルエンザ)のケースです。 当時から既に安否確認サービスを利用したBCPを策定している企業があり、金融や製造業、住宅サービスなど幅広い業種で実施されました。
これら企業は当時どのようなメッセージを社員に送り、活用していたのでしょうか?
- 健康・体調を確認する質問を毎朝送信
- 日本国内の感染状況および注意喚起の連絡
- 感染した場合など、状況によって出社禁止の指示
このような内容を定期的に送ることで、社内の状況を速やかに把握することができたのでした。安否確認ツールは各社員へ即座に情報を伝えることができ、自動配信の機能によって手間を掛けることなく日次で状況把握することもできるのです。
おわりに
BCP対策は、自然災害だけでなく感染症においても有効です。そして、感染症に対するBCPは平時の時の感染症予防や人員不足時の対応などにも有効であるため、ぜひ計画は策定しておきましょう。
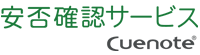 キューノート
キューノート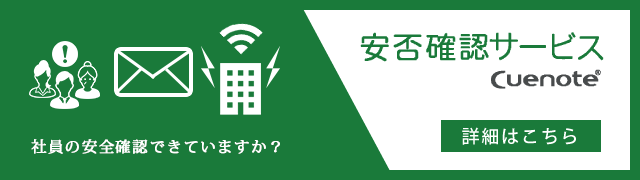
 安否確認訓練はなぜ必要?目的や効果的な実施ポイント・流れについて解説
安否確認訓練はなぜ必要?目的や効果的な実施ポイント・流れについて解説
 企業が行う安否確認とは?目的やツールの選定方法を紹介
企業が行う安否確認とは?目的やツールの選定方法を紹介
 【2025年最新】企業でのBCP普及率は?対策に役立つツールも紹介!
【2025年最新】企業でのBCP普及率は?対策に役立つツールも紹介!
 安否確認サービス・システムのメリットを徹底解説
安否確認サービス・システムのメリットを徹底解説



