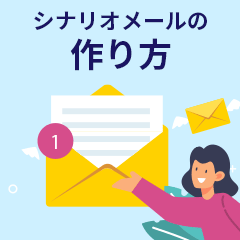アンケートで選択式の設問は奥が深い。コツと基本設計を解説
企業が行う安否確認とは?目的やツールの選定方法を紹介
関連製品:

地震・台風・ゲリラ豪雨に噴火など、日本にはさまざまな自然災害があります。さらに新型コロナウイルス感染症のように、予期せぬ災害が発生することもあります。企業側においては、事業を継続するためにも従業員などの安否確認の必要性が高まっています。
当記事では企業が行うべき安否確認の目的や方法、またツールの選定方法について解説していきます。
迅速・確実・簡単に安否確認を
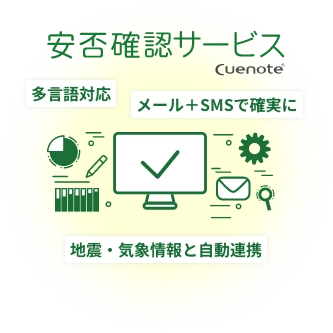
Cuenote安否確認サービスは、地震・自然災害発生時や、気象情報の発表に応じて自動通知を行い、安否確認・緊急参集が行える企業向けのサービスです。
なぜ、企業が従業員の安否確認を行うのか?
企業や従業員が災害に見舞われた時、安否確認を行う目的は主に2つあります。
- 従業員の安全を配慮する必要があるから
- 被災後の事業の早期復旧に繋がる最初の1歩になるから
従業員の安全を配慮する必要があるから
前提として人として多くの時間を共にする従業員の安全を確認し、助け合うという倫理的・人道的な側面はあります。そのうえで、労働契約法や労働安全衛生法にて、安全配慮義務があります。安否確認の義務は定められていないものの、安否を確認することは求められています。
安否確認により、助けを求める従業員が判明すれば、支援を行うこともできます。特に拠点が複数ある場合には、被災を免れた拠点からさまざまな支援が可能になります。
被災後の事業の早期復旧に繋がる最初の1歩になるから
被災した人の本当の意味での復興は、元の生活またはそれ以上の状況に戻すことであり、「収入の安定」も必要です。被災後、身の安全が確保できたのち、適切に仕事復帰を行うことは重要です。そのためは、さまざまな災害・緊急事態に対してできる限り事業の継続と、早期の復旧が重要です。その1歩として業務に取り掛かれる従業員の確認も必要です。
安否確認で始まる、事業の継続・早期復旧とは
災害の規模により異なりますが、被災した後でも収入を確保するためには事業継続・早期復旧が必要です。一方、被災した方の中には、影響がなく直ぐに業務を行える人から、非難が必要のケースや、従業員もしくはその家族の命が脅かされる「業務どころではない人」もいます。
安否確認を取ることで、事業継続に向けて対応できるメンバーの確認や、助けを求める人に対して企業側からの援助を行うことができます。事前にBCP(事業継続計画)を定めていれば、安全が分かり業務が分かった人に、早期に事業継続・復旧を依頼することもできます。
またこのように事前に災害に対する対策が講じられていれば、顧客などの社会的な信頼度も向上します。
企業が従業員に対して安否確認を行うときの課題・問題点
被災した場合、すぐに従業員に対して安否確認を行うことは重要ですが、課題はさまざまあります。
繋がりやすい連絡手段と、繋がらない連絡手段が発生する
被災の規模・内容によっては、電話がつながらなくなることや、回線の混雑により繋がりにくいことも考えられます。特に、被災してから時間の経過とともに様々な人が連絡を取り合うこともあり、さまざまな連絡手段が取りにくい状況になる可能性があります。
過度な連絡は、避難者にとっては死活問題になる可能性も
被災時、連絡手段や状況把握のために携帯電話は必需品です。しかし、電気が通らない場合においては、過度な使用は電池を消耗させ、状況によっては連絡手段が途絶える死活問題に発展する可能性もあります。
そのため、企業は従業員に対して安否確認したいがために、過度に連絡を取ることは避けるべきでしょう。
従業員はまず家族など身内の連絡を優先すべきであるため、連絡が取りづらい
従業員は、会社の復旧・継続も重要ではありますが、それ以上に自身や身内の安全が重要です。そのため、電気や電話回線が取っている場合においても、繰り返し電話をするなどは避けるべきでしょう。
安否確認を行うための「安否確認サービス」とは?
安否確認サービスは「安否確認システム」とも呼ばれる、ツールのことを指します。アプリ・サービスを通じて、メールやSMS(ショートメッセージ)あるいはLINEなど、さまざまな手段を講じて連絡を取ることができます。
特徴として、地震発生や大雨などの気象災害時には気象データと連携して自動で安否確認メールを送ることができます。災害は時間の経過とともに連絡がつきにくくなります。また通知内容は、簡単なタップや設問回答で済むように設定できるため、被災者にとって連絡どころではない状況においても、低負担で回答しやすくなります。
安否確認サービスの主な機能
安否確認サービスは、確実性高く安否確認が行えるよう以下のような機能があります。
| 安否確認 | 災害が発生した際や予期せぬ緊急事態が生じた時に、確認・把握することができます。 |
|---|---|
| 自動再送信 | 回答できなかった従業員に自動で再送信できます。 |
| 災害時の緊急参集 | 救援活動が必要な際に、近隣団体や部署を指定しての召集が可能です。 |
| 障害時対応要請 | 障害発生時に緊急対応可能な所属員の募集、受諾確認が行えます。 |
| 欠員補充の対応 | 傷病、交通支障など欠員発生時の要員募集、受諾確認が行えます。 |
| メールアドレス存在確認 | 連絡先の有効性を確認でき、更新も簡単に行えます。 |
| 訓練メールの定期配信 | 定期訓練の実施により、災害発生時の課題を事前に確認できます。 |
| 出欠確認・調査 | イベントや集会の出欠確認も行え、回答状況は管理画面で確認可能です。 |
また、従業員への安否確認は「アンケート」としての側面もあるため、イベントや集会の出欠確認など、他の用途でも活用が可能です。
安否確認サービスの選び方
メールやSMSなど連絡手段の実績を確認
従業員の安否確認のメインはメールやSMSです。それぞれ「なりすましメール」も多く流通しているなどから、メーラーなどは迷惑メールの可能性がある場合には、到達しない場合や迷惑メールボックスに振り分けられるなど、正しく届けられないことも多々あります。
例えばメール配信システムや、SMS送信サービスなど連絡手段個々に対するサービスの実績があれば、配信性能は高いと言えます。重要なときに届かなければ意味がありませんので、なるべく実績の高い企業を選びましょう。
連絡手段は最適化どうか
例えばLINEで通知を送ることができるツールもあります。一方で従業員側においてLINE通知を敬遠するケースもあるでしょう。どのような連絡手段ができ、どのような連絡手段が従業員にとって使われやすいかを考えると良いでしょう。
訓練・シュミレーション機能があるかどうか
いざとなった時に利用する安否確認は、日ごろの訓練も重要です。ただし、訓練は本来生産性のある業務ではないため、手軽に訓練ができるかなどは、選ぶときのポイントになります。
さいごに
安否確認は、今や多くの企業にとって欠かせないツールになってきています。メール配信システムやSMS送信サービスなどで、各連絡手段の実績もある当社も「安否確認サービス Cuenote」を提供しています。ぜひお問合せください。
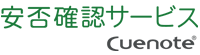 キューノート
キューノート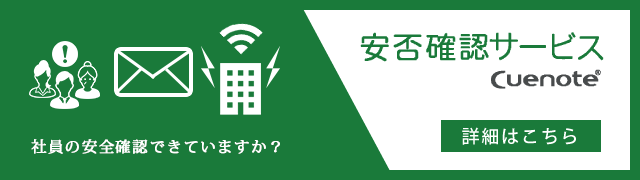
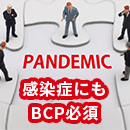 感染症にもBCP必須!初動対応は安否確認サービスが有効
感染症にもBCP必須!初動対応は安否確認サービスが有効
 【2025年最新】企業でのBCP普及率は?対策に役立つツールも紹介!
【2025年最新】企業でのBCP普及率は?対策に役立つツールも紹介!
 安否確認サービス・システムのメリットを徹底解説
安否確認サービス・システムのメリットを徹底解説