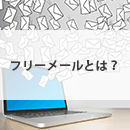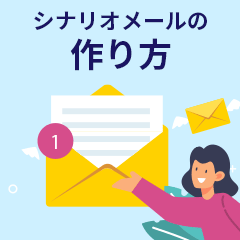メルマガ×SEO対策でコンテンツマーケを最大化
RFM分析とは?購買データを元に戦略的な施策に繋げる方法を解説

難しそうな印象のあるRFM分析は、購買データを元に購買行動を分析する有効なマーケティング手法のひとつです。当社が提供しているメール配信システム「Cuenote FC」でもRFM分析ができる内容のため、実践頂けるように分かりやすく解説していきます。
メールマーケティングを
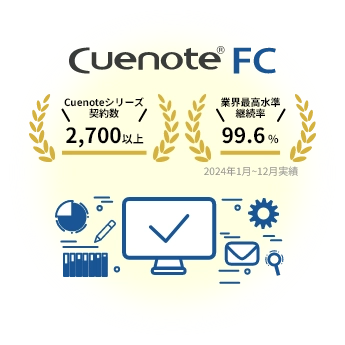
Cuenote FCはハイスピードな大量配信を得意としながら、効果測定や自動処理も可能で大手企業にも選ばれるメール配信システムです。メールマーケティング機能も豊富で、配信数上限はなく送り放題です!
RFM分析とは?
RFM分析は、主に3つの購買データを元に顧客の傾向を分析することで、売上向上・改善に繋げる手法のことを指します。 3つの購買データとは、RFMのそれぞれの頭文字を取る形で以下の通りです。
- R:Recency(最新購買日)
「どれくらい最近購入したか」を示します。例:1週間前に購入したユーザーはRが高い、1年前ならRが低い。 - F:Frequency(購買頻度)
「どれくらい頻繁に購入しているか」の指標。例:過去1年で10回以上購入している人はFが高い。 - M:Monetary(累計購買金額)
「どれくらいお金を使ったか」を表します。例:高額商品を何度も購入している人はMが高い。
RFM分析が実際どんな役に立つのか?
RFMの3つの要素を組み合わせることで「優良顧客」や「離反見込みの顧客」などのユーザー像を把握でき、数値に基づいた改善が行えます。
例えば、購買頻度や購買金額が高い層でも、最新購買日が1年以上前であれば、元優良顧客が離反している可能性があります。この層が全体顧客から見て割合が多ければ優先的に対策する必要があると考えられます。
また累計購買金額が少なくとも、高頻度で購入してもらっている層が多ければ、単価を上げる取り組みをすると売上向上に大きく影響する可能性があります。このようにRFM分析をすることで定量的に分析して改善を行うことができます。
RFM分析のメリット
RFM分析の具体的なメリットについても解説します。
顧客の「状態」が定量的にわかる
役立つ部分で解説した通り、顧客の属性や傾向が見えます。Fが高くMの低い企業が多いのか、その逆が多いのかなどを分析することができます。
特にRFM分析を定期的に確認することで、この状態の変化にも気づきやすくなります。
再購入・クロスセル・アップセルの戦略が立てやすい
RFM分析は、購入頻度や購入金額といった具体的な購買データに基づいて顧客を分類するため、再購入・クロスセル・アップセルといったマーケティング戦略を立てやすくなります。
例えば、新商品を発売した際には、購入頻度が高い顧客に限定したキャンペーンを展開することで、クロスセルを効果的に狙うことができます。 また、最終購入日から時間が経過している顧客に対しては、再購入を促すためのクーポン配布やリマインド施策などが有効です。
このように、RFM分析は顧客の購買状況に応じたグルーピングを行うため、「誰に」「何を」提案すべきかが明確になり、より効果的なアプローチが可能になります。
キャンペーンの効果検証にも有効
離反傾向にある顧客に対して再購入を促すクーポンを送る場合、真のゴールは単なる購入ではなく、離反の防止=顧客の再リピート化にあります。
RFM分析を定期的に観測することで、「最終購買日が遠のいている顧客」が施策後にどれだけ減少したか、また購入頻度にどのような変化があったかを把握できます。
RFM分析を行う手順
① データを準備する
顧客の購買履歴データを準備します。最低限、以下の情報が必要です。
- 顧客ID
- 購入日
- 購入金額
これらの情報があることで、顧客ごとに「最終購入日」「購入頻度」「累計購入金額」を算出できます。
② R・F・Mの指標を計算する
次に、顧客ごとに以下の3つの指標を計算します。
- Recency(リセンシー):最後に購入した日から、現在までの経過日数
- Frequency(フリークエンシー):一定期間内の購入回数
- Monetary(マネタリー):一定期間内の累計購入金額
これらを計算することで、顧客の「最近どのくらい購入しているか」「どのくらいの頻度で買っているか」「どのくらいお金を使っているか」が分かります。
③ スコアを付ける
R・F・Mそれぞれの値にスコア(1~5点など)を付けます。
たとえばRecencyが新しいほど高得点(例:最近購入した人は5点)、購入頻度が高いほど高得点、購入金額が多いほど高得点などです。
これにより、顧客ごとのRFMスコア(例:R=5, F=4, M=5など)が算出されます。
④ 顧客をグループに分類する
RFMスコアをもとに、顧客をいくつかのグループに分類します。
- RFM全てにおいて5点の顧客:もっとも価値の高い「優良顧客」
- RFM全てにおいて1点の顧客:離反している可能性のある顧客
- Fは高いがRが低い顧客:以前は常連だったが最近は購入していない「休眠顧客」
このように分類することで、ターゲットごとに施策を立てやすくなります。
⑤ 施策の立案・実行
分類した顧客グループに応じて、マーケティング施策を立てます。
- 優良顧客に対して:ロイヤルティプログラムや限定オファー
- 休眠顧客に対して:再購入を促す割引クーポン
- 新規顧客に対して:継続購入を促すフォローアップメール
⑥ 効果を検証・改善する
施策を実施した後は、再度RFM分析を行い、どのグループの動きに変化があったかを確認します。改善の余地があれば、次の施策に活かしていきます。
RFM分析の結果から行うべき施策
| 属性 | R | F | M | 行うべき施策 |
|---|---|---|---|---|
| 優良顧客 | 高 | 高 | 高 | ロイヤリティ向上のプログラムなど |
| 新規顧客 | 高 | 低 | 低 | 継続的な購入を促す、クーポンなど |
| 休眠顧客 | 低 | 中 | 中 | 再購入促進のための限定クーポンや特別オファー |
| 離反顧客 | 低 | 低 | 低 | 無料サンプル配布、クーポン配布など |
RFM分析の結果からは、上記のような施策が考えられます。分析を細分化することや、購買する商品の傾向なども含めることで、より細かい施策に落とし込むことも考えられます。
特に、優良顧客においてはファンになってもらうことで、新たな顧客を呼び寄せる可能性があります。また休眠・離反顧客の中には、商品に興味関心はあるものの、記憶から薄れてしまっている、購入を忘れているなども考えられます。適切にアプローチすることで機会損失を防止することができます。
RFM分析の注意点
分析期間の設定に注意
RFM分析では、購入履歴の分析期間が短すぎると顧客の購買傾向を正確に把握できず、長すぎると古いデータが現状を反映しにくくなります。適切な期間設定が重要です。
未来の行動予測には限界がある
過去の購買データをもとに分析するため、顧客の将来の購買行動を完全に予測することはできません。ほかの分析手法と組み合わせることが効果的です。
優良顧客や離反顧客への対策は劇的にはならない
優良顧客は既に強い関係性や満足度がある可能性があり、劇劇に売上が上がるということは考えにくいです。また離反顧客に対しても、0にすることはできず、一定数発生します。理由によっては引き留めが難しいものもあり、過剰な対応は他の顧客との待遇差による満足度低下の可能性もあります。
RFM分析したら、メールマーケティングで訴求
メルマガなど、メールで販促活動を行う「メールマーケティング」はRFM分析との相性は非常に良いものがあります。
優良顧客に対してのロイヤリティプログラムの案内や、離反顧客に対するクーポンも、対象顧客のみに絞った一斉配信を行うことで、効果的に訴求することができます。特に当社が提供しているメール配信システム「Cuenote FC」では、RFM分析に必要なデータを取り込むことで、分析した結果をターゲット選択して、メール配信することができます。
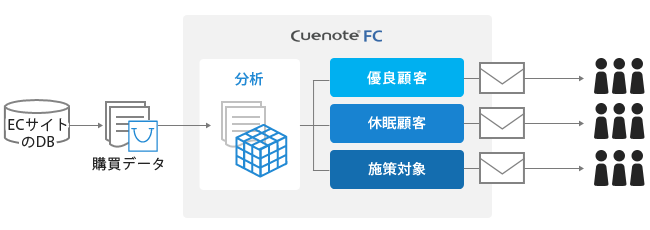

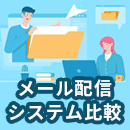 【2026年最新】メール配信システム比較17選!種類や機能・目的別選び方を徹底解説
【2026年最新】メール配信システム比較17選!種類や機能・目的別選び方を徹底解説
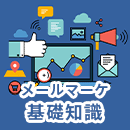 【2026年版】メールマーケティングとは?最新調査から基礎やメリット・KPIなどを完全解説
【2026年版】メールマーケティングとは?最新調査から基礎やメリット・KPIなどを完全解説