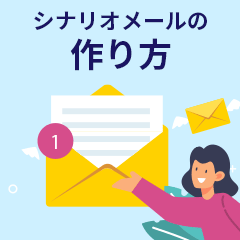アンケートの自由記述を効果的に活用するコツとは?分かりやすく解説
BIMIとは?認証の仕組みやなりすまし対策の効果を解説
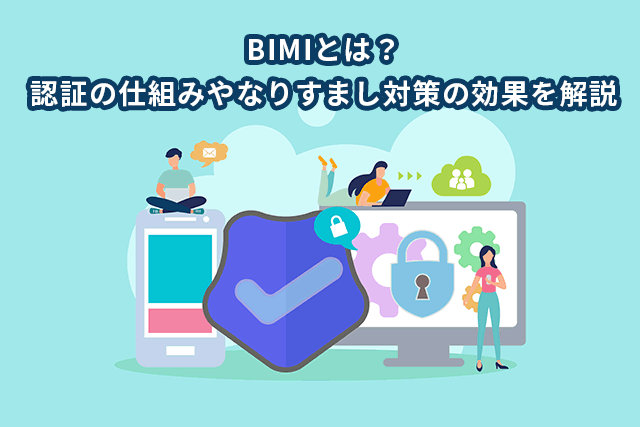
多くの人が利用しているメールは、「迷惑メール・なりすましメール」の問題があります。受信者においては、ウイルス感染や詐欺の被害を受ける可能性があり、メルマガ担当者には開封率を低下の要因となる大きな問題です。
そこで、メールの利便性を向上するため、さまざまな迷惑メール対策が普及しています。その中でも注目されているのが「BIMI」です。Apple(iCloudメール)、Google(Gmail)、Yahoo!(ヤフーメール)など対応しているメーラーは年々増えています。
当記事では、なりすまし対策として推奨されるBIMIについて認証の仕組みや導入のメリット、設定方法など解説します。
メールマーケティングを
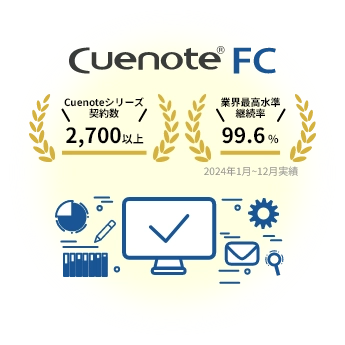
Cuenote FCはハイスピードな大量配信を得意としながら、効果測定や自動処理も可能で大手企業にも選ばれるメール配信システムです。メールマーケティング機能も豊富で、配信数上限はなく送り放題です!
BIMIとは
BIMI(Brand Indicators for Message Identification)とは、その送信元から送られている正規のメールであることを示すために、自社やサービスのロゴマークをメールに表示させる仕組みです。
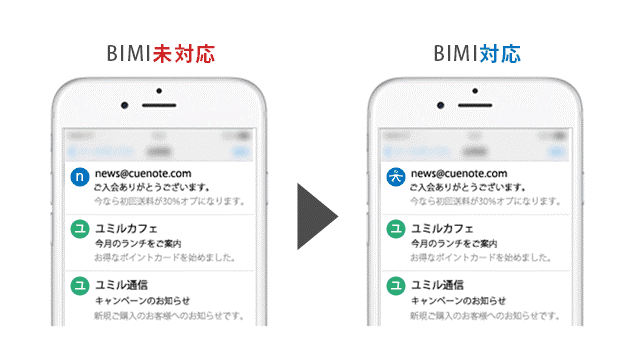
上の画像のように、BIMIの設定がされていない今までの場合には、アカウント名の頭文字やイニシャル等が表示されます。BIMIの設定がされている場合には右図のようにあらかじめ設定したロゴが表示されるようになります
今までのメール認証技術とは異なり、受信者はヘッダー情報などを読まずに視覚的に認証対応がされているか確認できるため、注目の仕組みです。
BIMIによる送信元認証の仕組み
BIMIは、受信したメールがSPF・DKIMの認証に合格した、なりすましや改ざんされていない状態で、DMARCで相手に受け取らない配慮などがされている場合に、その証拠としてブランドロゴが表示されるという仕組みです。
そのため、BIMIの適用にはDMARCの設定が必要となります。DMARCの設定後にDNSにBIMIレコードを追加し、企業のブランドロゴのURLを指定します。メールのプロバイダーは受信したメールがDMARCとBIMIそれぞれの要件を満たしているかを確認し、満たしている場合のみ送信元のブランドロゴを表示するという流れです。
その他の送信元認証
BIMIの利用には、「SPF」「DKIM」「DMARC」の認証をしている必要があります。以下ではそれぞれの認証について簡単に解説します。
SPF(Sender Policy Framework)
なりすまし・迷惑メール対策として、IPアドレスを利用して受信したメールの送信元が詐称されていないかどうかを確認することができる標準的な送信ドメイン認証技術の一つです。
SPFの仕組みは、メールの送信元となるサーバーのIPアドレス(またはドメイン名)をDNSに登録し、公開することで、メールを受信したサーバーはメールアドレスのドメイン名を使ってDNSに登録されたSPFの設定を調べ、送信元が設定されているIPアドレスと一致するかを確認します。一致していれば正規のメールサーバーからのメールと判別しますが、一致しなければ、第三者のメールサーバーからなりすまされて送信されたメールと判別するという仕組みです。
DKIM(DomainKeys Identified Mail)
なりすまし・迷惑メール対策として、電子署名を利用して受信したメールの送信元が詐称されていないかどうかを確認することができる送信ドメイン認証技術のこと。
DKIMの仕組みは、まず送信者が電子署名に使用する公開鍵をDNSサーバーで公開します。次にメールを送信する際、メール送信サーバーで秘密鍵を用いて送信メールに電子署名を付与し、 そのメールを受信したメール受信サーバーは、署名ドメインのDNSサーバーに問い合わせをして公開鍵を取得し、署名を検証します。一致しなければ、なりすましやメールの改ざんを検知します。
DMARC(Domain-based Message Authentication, Reporting & Conformance)
フィッシングメールやスパム等の迷惑メール対策のため、Google、Facebook、Microsoftらが参加するワーキンググループが定義したレポーティングとポリシー制御のための技術仕様のことです。 送信者と受信者の間でメールの正当性を確認するための送信ドメイン認証は、DKIMとSPFの両方の技術を用いて行います。
BIMIの判定にはDMARCを採用
BIMIにおいて前提となる「送信元が詐称されていないか」の判断には、送信元ドメイン認証の仕組みであるDMARCが用いられます。
DMARCは、送信元ドメイン認証技術のSPFおよびDKIMにより「なりすましメール」と判定されたメールに対する受信側の取り扱いを定義(ポリシー宣言)する仕組みで、「そのまま受信する(none)」 「受信したうえでスパム扱いする(quarantine)」「拒否する(reject)」の3種類から取り扱いを定義することができます。
ここで言う「なりすましメール」は、『DMARCがより参照しているSPFおよびDKIMによる認証のいずれにも失敗したメール』を指します。但し、これには『なりすましではないけどSPFおよびDKIMいずれの設定もされていない」メール』も含まれます。
現在、日本国内におけるDKIMの普及率は50%程度であるもののSPFの普及率は90%程度とされており、ほとんどのメールがいずれかの認証には成功する一方で、裏を返せば全体の最大1割程度は認証に失敗する可能性があるということです。 そのため、「拒否」扱いとした場合になりすまされていないメールも正しく受信できなくなるリスクが存在します。
しかしながら、BIMIはその適用対象を「DMARCポリシーで『拒否』と定義されたドメイン」に限定しています。すなわち、「未設定も含めて認証できないドメインからのメールを受け取らない」 という強力ななりすまし対策水準を設ける必要があり、当然ながら送信側自らが正しくDMARC対策を行わなければなりません。
後述する通りBIMIへの対応は、なりすまし対策だけでなく、レスポンス率の向上にもつながります。
BIMIは送信者側にとってどう役立つのか
BIMIはなりすまし対策として実装されており、その本義は「受信者が正規の送り元か否かを視覚的に判別しやすくする」点にあることは言うまでもないでしょう。
以下では、送信者側にとってBIMIに対応するメリットを解説します。
正規ブランドとしての安心感を与えられる
一般に、画像は文字の10倍近い情報量を持つと言われています。また、送信者名やアドレス、件名などはどのような名称を騙っても問題無い一方で、BIMIは認証済みの送信元でないと対応できないこともあり、 アイコンやロゴが画像として表示されていることの安心感は特に高いと言えます。
メールの反応率がアップする
BIMI対応によって送信者側として特に期待できるのは「受信トレイ内で目立つようになり、反応アップが期待できる」点ではないでしょうか。
上記の調査結果からわかる通り、ビジネスでも既に3分の1が、プライベートでは過半数がメール閲覧環境として「スマートフォン」を利用しています。 また、PCからの閲覧でもWebメールクライアントを利用する場合、スマートフォン同様にBIMIへの対応が可能です。
ただでさえ文字の羅列であることの多い受信トレイにロゴやアイコンがあれば、それだけで目を引く要素になり得ます。さらに今はまだ対応している送信元事業者が多くない段階でもあり、 より視覚的な訴求効果が高いタイミングとも言えます。現時点では、受信トレイ内で表示できるリッチコンテンツは「件名・プリヘッダーの絵文字」と「BIMI対応によるアイコン・ロゴ画像」しかなく、 「開封前に高い訴求力を持つ」数少ないコンテンツの1つとしても、送信側にとって活用価値は大いにあると考えられます。
なりすまし被害を事前に防げる
なりすましメールによる受信者の被害となりすまされた企業の被害は年々増えています。もちろん受信者側のメールサービスプロバイダーがBIMIに対応していることが前提にはなりますが、 受信者は瞬時になりすましメールと正規メールを見分けることができるようになるため、迷惑メールとして登録されたり報告されるようなことが少なくなります。
BIMIの設定方法(送信者側)
BIMIを設定する手順は以下の流れになります。
- SPF・DKIM・DMARCの設定を行う
- ロゴを作成する
- ロゴの証明書を取得する
- BIMIレコードをDNSに追加する
- BIMIレコードを確認する
各プラットフォーム・事業者における対応状況
現時点でBIMIはインターネット技術の標準化を推進する任意団体「IETF」が公表する草稿文書の段階であるため、正式な規格(RFC)として定義されていない状態です。しかしながら、2021年7月にGmailが対応を開始したのに続き、2022年秋よりMac OS及びiOSでのサポートが開始されました。
BIMIはそれ自身というより、その前提となるDMARCへの対応において送信側事業者に一定の手間を必要とするものでありますが、受信トレイを司るプラットフォーム側での対応が進むことによって、本格的な普及の足掛かりとなることが期待されています。
ECを運営する事業者のBIMI対応状況(2024年時点)
弊社で独自に行った日本でトップ50の売上のあるEC事業者のBIMI対応調査では4.7%という結果になりました。GmailのBIMI対応から4年近くたちますが、対応している企業の方が珍しい状況です。
BIMIは他の送信元認証技術と比べても設定の手間がかかるため、対応までのハードルが高めとなるため未対応の企業がまだ多い状況です。
大手企業もまだ未対応という点を逆手に取り、BIMIに対応することで差別化できることもあるため、気になる方はこの機会にBIMIの利用を検討するとよいでしょう。
今後、各送信者ガイドラインなどに適用される可能性も
2025年3月時点で、正式に発表されているメールサービスは確認できておりませんが、将来的にはGmailなどの送信者ガイドラインに要件として追加される可能性も考えられます。
なぜなら、各メールサービスは、迷惑メールやなりすましメールをなくし、安心してメールのやりとりが出来るよう改善しているためです。Gmailの送信者ガイドラインは、2024年2月よりSPFやDKIM、DMARCなどの対応を求めるようになりました。その先にあるBIMIも将来的に対応を求められる可能性もあるでしょう。
まとめ
今回は、なりすまし対策の一環として普及が期待されるBIMIについて、その仕組みと効果を解説しました。
最近Yahoo!でもBIMIに対応した話題がありますが 、同社サービスは特に積極的にメールによるプロモーションを活用しており、Yahoo! を騙る正規でない送信元からの被害を防ぐため、受信者保護の観点から導入に至った経緯があります。
Webマーケティングの進展によりメールの送信数量も増えていますが、活発なメールコミュニケーションを実施していたり、販促チャネルとして重視していたりする場合にはなおさら、
なりすまし対策をはじめとしたメールセキュリティの強化が求められます。
ロゴ・アイコンの表示による反応向上の効果も含め、送信者側のより一層の取り組みに期待です。
- 関連する記事
-
-
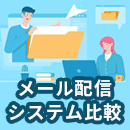 【2026年最新】メール配信システム比較17選!種類や機能・目的別選び方を徹底解説
【2026年最新】メール配信システム比較17選!種類や機能・目的別選び方を徹底解説
-
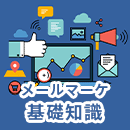 【2026年版】メールマーケティングとは?最新調査から基礎やメリット・KPIなどを完全解説
【2026年版】メールマーケティングとは?最新調査から基礎やメリット・KPIなどを完全解説
-
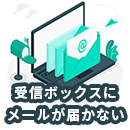 受信ボックスにメールが届かない原因と解決策をご紹介!【2026年最新】
受信ボックスにメールが届かない原因と解決策をご紹介!【2026年最新】
-
 メールサーバー・メール配信の仕組みと選び方を徹底解説
メールサーバー・メール配信の仕組みと選び方を徹底解説
-
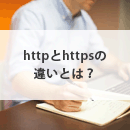 httpとhttpsの違いは何? Webサイトで必須のセキュリティを解説
httpとhttpsの違いは何? Webサイトで必須のセキュリティを解説
-
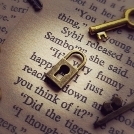 ドコモメールが「DKIM」「DMARC」に対応、より高精度ななりすまし対策が可能に
ドコモメールが「DKIM」「DMARC」に対応、より高精度ななりすまし対策が可能に
-
 65%以上が東日本大震災で事業縮小するなど。今、災害復旧のDR(ディザスタリカバリ)が注目される理由
65%以上が東日本大震災で事業縮小するなど。今、災害復旧のDR(ディザスタリカバリ)が注目される理由
-
 ドコモメールが「公式マーク」対応をスタート、適用メリットや仕組み、その方法は?
ドコモメールが「公式マーク」対応をスタート、適用メリットや仕組み、その方法は?
-