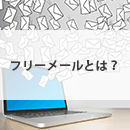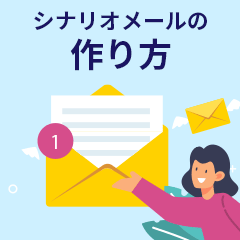メルマガ×SEO対策でコンテンツマーケを最大化
ビジネスメール書き出しのマナーや注意点~初めての送信時に使える例文をご紹介~
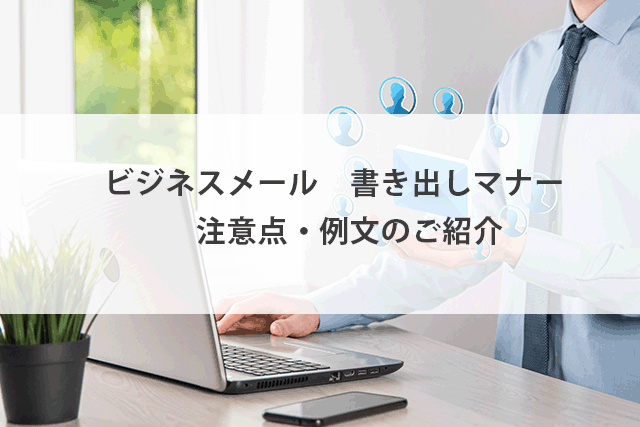
ビジネスメールの書き出しは、読み手に対して最初の印象を与える重要な要素となり、ビジネスパートナーやお客様にとって最初の接点となるため、正しいマナーで記載し、丁寧で適切な表現を心がけることが求められます。
本記事では、ビジネスメールの書き出しルールや基本マナーに沿った例文まで紹介しますので、ビジネス上でのスムーズなメールコミュニケーションに役立てていただければと思います。
メールマーケティングを
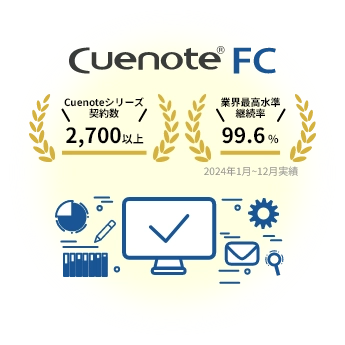
Cuenote FCはハイスピードな大量配信を得意としながら、効果測定や自動処理も可能で大手企業にも選ばれるメール配信システムです。メールマーケティング機能も豊富で、配信数上限はなく送り放題です!
ビジネスメールの基本マナーと注意点
ビジネスメールの書き出しは、ある程度決まった形式で記載され、正確な文体や丁寧な表現、幾つかの基本的なマナーを守ることが求められます。ここでは書き初める前に知っておくべき、幾つかのルール・マナーを解説します。
「拝啓」や「敬具」などの頭後・結語は省略する
ビジネスメールは郵送の手紙とは異なり、文頭・文末に記載する「拝啓」「敬具」などの言葉を入れる必要がありません。
ビジネスメールは、簡潔に要点をまとめて伝える、ということが目的となり、相手に読む負担を掛けないことも求められますので、型式的な語句は省略して「宛名」から書き始めるのがマナーとなります。
宛名を決められた順番で正しく記載する
ビジネスメールの冒頭には、まず「宛名」を記載しますが、相手方が企業に属している場合は、会社名(正式名称)、部署、氏名(または苗字のみ)を、以下の順番で正しく記載するのがマナーとなります。
ビジネスメールの宛名に記載する内容
- 会社名 ※正式名称
- 部署名、役職名
- 氏名(フルネーム、又は苗字のみ)
2回目以降のやり取りで関係性が出来ている相手方には、社名や部署名を省略するケースもありますが、初めてのメールでは上記を順番通りに記載し、社名や氏名の漢字に誤記がないよう注意しましょう。
挨拶と送信者の情報(会社名、部署、氏名)を記載する
ビジネスメールでは、本題に入る前に一言の挨拶を入れることがマナーです。社内、社外それぞれで適切な挨拶文と自己紹介を記載しましょう
社外・お客様宛の場合の一例
社外向けの挨拶文→自己紹介(会社名・部署・氏名)を記載します。
- お世話になります、〇〇株式会社〇〇部の〇〇と申します。
- いつもお世話になっております。〇〇株式会社〇〇部の〇〇でございます。
社内・関係者宛の場合の一例
社内向け挨拶文→自己紹介(部署・氏名)を記載します。
- お疲れ様です、〇〇部の〇〇です。
- おはようございます、〇〇部の〇〇です。
次に、これらの基本マナーを踏まえ、シチュエーション使える、幾つかの例文をご紹介します。
シチュエーション別:ビジネスメール書き出しの例文【社外宛て】
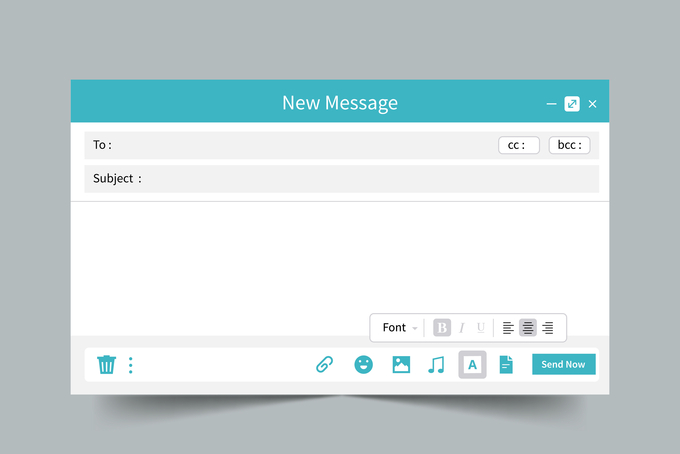
基本的なマナーを踏まえて、シチュエーション別に幾つかの例文を紹介しますので、参考にしていただければと思います。
初めてのメール連絡
・突然のご連絡を失礼いたします。〇〇株式会社〇〇部の〇〇と申します。
この度は、弊社までお問合せいただき、誠にありがとうございます。
・突然メールを差し上げますこと、失礼いたします。
〇〇株式会社〇〇部の〇〇と申します。
この度は、資料請求いただきまして、誠にありがとうございました。
・初めてご連絡を差し上げております。、〇〇株式会社〇〇部の〇〇と申します。
この度は、〇〇様からのご紹介によりご連絡させていただきました。
初めてメールを送る相手には、「お世話になっております。」などの既に関係性がある相手用の言葉は使わないように注意しましょう。
また相手からすると、突然面識のない相手からメッセージが届くことになりますので、突然知らない相手からメールが送られてくることに対して、配慮の言葉を入れるのが適切です。
また、そのなぜメール連絡を行ったか、といったきっかけや経緯簡潔に記載しておくと相手に安心感を与えることができ、警戒心を解くきっかけになります。
2回目以降のメール連絡
- いつもお世話になっております。〇〇株式会社〇〇部の〇〇と申します。
- 平素より大変お世話になっております。〇〇株式会社〇〇部の〇〇と申します。
- 大変お世話になっております。〇〇株式会社〇〇部の〇〇と申します。
2回目以降のメール連絡では、これらの書き出しにするのが一般的です。複数回やり取りを行ってある程度関係性のできている相手には、「お世話になっております。」を使ったり、部署名・社名を省略することもありますが、その様な場合でなければ、基本的には上記の書き出しとしましょう。
期間を空けてのメール連絡
- お久しぶりです、その後はいかがお過ごしでしょうか。
- 長らくご無沙汰をしておりまして、申し訳ございません。
- ご無沙汰しております。〇〇の件では大変お世話になりました。
「ご無沙汰しております」はより丁寧な印象となりますが、関係性が出来ている親しい相手には、「お久しぶりです」を使い、以前お世話になった件へのお礼などを添えておくことで、相手に思い出してもらうきっかけとなり好印象を与えられるでしょう。0
複数回連続でメール連絡する場合
- 度々のご連絡となり、失礼いたします。
- 何度も重ねてご連絡してしまい、申し訳ございません。
- 五月雨式にご連絡差し上げ、失礼いたします。
1度目の連絡後、追加情報や資料送付などが発生し、複数回連続でメール連絡が必要になるケースもありますが、その場合、連続でメール送付することへ配慮する言葉を冒頭に入れましょう。このような言葉を冒頭に記載した場合、「お世話になっております」などの挨拶文は省略しても問題ありません。
相手方からのメール連絡に対して返信する場合
- ご連絡くださいまして、ありがとうございます。
- 迅速なご返信を賜り、誠にありがとうございます。
- 早速ご返信いただき、誠にありがとうございます。
お客様やビジネスパートナーからのメールなどに返信を行う場合、冒頭にお礼を記載しましょう。「迅速な」や「早速」などの言葉を入れることで、よい印象を与えられますので記載するとよいでしょう。
1度目の連絡後、追加情報や資料送付などが発生し、複数回連続でメール連絡が必要になるケースもありますが、その場合、連続でメール送付することへ配慮する言葉を冒頭に入れましょう。「お世話になっております」などの挨拶文は省略しても問題ありません。
感謝の気持ちを伝える
- この度は貴重なお時間をいただき、誠にありがとうございました。
- 日頃のお力添えに、心より感謝申し上げます。
- この度はご協力をいただきまして、誠にありがとうございます。
打合せの参加や資料作成など、相手方に何かしらの作業や調整を行ってもらった場合は、冒頭で感謝の気持ちを丁寧に記載するとよいでしょう。
お詫びや謝罪を行う場合
- この度は、多大なるご迷惑をお掛けしてしまい、誠に申し訳ございません。
- 〇〇の件におかれましては、ご関係各位にご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございませんでした。
- この度は、弊社(私)の不備により大変なご不便とご心配をお掛けし、誠に申し訳ございません。
ビジネスメールでは、「お詫び」を行わなければならないケースも多くあると思いますが、そのようなときも具体的な謝罪内容に触れるメールの冒頭では、丁寧に相手方に対してお詫びの言葉を記載するとよいでしょう。相手方がメールを読み進める際の心情に配慮することが重要です。
シチュエーション別:ビジネスメール書き出しの例文【社内宛て】

ここからは職場内の上司や役職者、同僚などの社内関係者や、目上の人に対してメールを送る場合の例文をご紹介します。
社外やお客様より砕けた言い回しで問題ありませんが、礼儀やマナーをしっかり把握し、社内コミュニケーションを円滑に行いましょう。
同僚や上司宛てにメール送信する場合の書き出し
- お疲れ様です、〇〇部の〇〇です。
- (午前中の場合)おはようございます、〇〇部の〇〇です。
- (勤務時間外の場合)勤務時間外でお忙しい所、失礼いたします。
上司や同僚の社内関係者にメールする場合、「お疲れ様です」と記載しておけば問題ありませんが、メール送信する時間帯や状況などに配慮し、書き出しを工夫できると良い印象を与えらます。
また、「ご苦労様」という言葉は目下の立場の人に対して使う言葉ですので、上長や同僚に対しても使わないのが一般的です。
複数名に対してメールを送る場合の書き出し方

ビジネスでは、その業務やプロジェクトなどにより、複数名を宛先(ToやCC、BCCなど)に含めて送信するケースが多くありますが、その場合の宛先の書き方や、書き出し方についても解説します。
まず、メール送信時の宛先指定は、用途に応じて以下3つを使い分ける必要があります。
「To」「CC」「Bcc」の使い分け
- To:処理や作業を依頼したい宛先のメールアドレスを指定
- CC:情報共有したい、関係者のメールアドレスを指定
- Bcc:情報共有はしておきたいが、送信先には伏せておきたいメールアドレス
※詳細は、別記事「 メールの「CC」「BCC」とは?」で解説しています。
宛先の用途を理解した上で、複数名にメールを送信する場合のルールやマナーを見ていきましょう。
複数名にメールを送信する場合の宛先の指定方法・書き出し
宛先に複数名を指定してメール送信する場合、本文冒頭の宛名も適切に記載しましょう。
To、CCを含め、宛先に4-5名程度の宛先を指定する場合、役職や会社の立場が上の人から順番に宛名を記載するのが一般的です。
宛先が5名以内の場合
XXXXX株式会社
XXXX部 〇〇様、△△様、□□様
CC:●●様、▲▲様
いつもお世話になっております。
〇〇株式会社、〇〇部の〇〇と申します。
~~~本文・依頼内容を記載~~~
宛先が6名以上の大人数になる場合や、2回目以降の連絡時は、主担当などの依頼先の人を宛名に記載し、残りの担当者をCCに含め、「関係各位」などの宛名とします。
宛先が6名以上の場合
XXXXX株式会社
XXXX部 〇〇様
CC:ご関係各位
いつもお世話になっております。
〇〇株式会社、〇〇部の〇〇と申します。
~~~本文・依頼内容を記載~~~
宛先の会社が複数ある場合は、それぞれの会社名とお名前を宛名に記載します。順番は1社に送るときと同様に、関係性や立場が高い会社から記載しましょう。(例:お客様と協力会社が宛先に含まれる場合、1.お客様、2.協力会社の順となります。)
宛名の記載方法以外のマナー・ルールは、基本的には本記事前半と同じです。社外・社内どちらも、対応をお願いしたい人のお名前を宛名に記載して、誰に対しての依頼事項なのかをしっかりと宛先の関係者に示すとよいでしょう。
補足:一斉配信にBCCを使うのは危険?安全に一斉配信する方法
「BCC」は送信先の相手に伏せて複数メールアドレスを指定できますので、複数企業、担当者を「BCC」アドレスに指定して一斉配信されているケースもありますが、誤って「CC」に宛先のメールアドレスを記載して送信してしまいますと、送信先メールアドレス全件に対して宛先の全メールアドレスが漏洩してしまいます。
ビジネスで利用される担当者メールアドレスも、大切に取り扱うべき「個人情報」となりますので、その様な事故を起こさないため、全く関係のない複数企業に対して同一のメールを一斉送信する場合は「BCC」を利用しない方法で行うのが安全です。
メールマガジンや、お知らせなど、取引先へのメール一斉送信には、その様な用途に特化した「メール一斉配信サービス」を利用しましょう。
まとめ
本記事では、ビジネスメールの書き出し方のマナーから、幾つかのシチュエーション別に例文をご紹介させていただきましたが、いかがでしたでしょうか?
ビジネスシーンでは、様々な業務をこなしながら忙しい相手方に対して、「正しく・簡潔」に要点を伝えなければならない一方で、様々な取引先のお客様や企業、その関係性に配慮したメールの書き出しを記載しなければなりません。
状況や連絡手段を問わず受け手に配慮したメッセージを送信するのは当然ですが、メールは文字だけで相手方に伝わりますので、意図せずにマナー違反な内容を送信してしまい、受け手の心象を損ねてしまわないための基本的なマナーとして、本記事をお役立ていただければと思います。

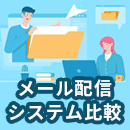 【2026年最新】メール配信システム比較17選!種類や機能・目的別選び方を徹底解説
【2026年最新】メール配信システム比較17選!種類や機能・目的別選び方を徹底解説
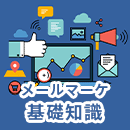 【2026年版】メールマーケティングとは?最新調査から基礎やメリット・KPIなどを完全解説
【2026年版】メールマーケティングとは?最新調査から基礎やメリット・KPIなどを完全解説