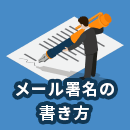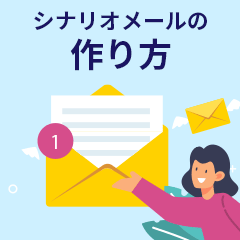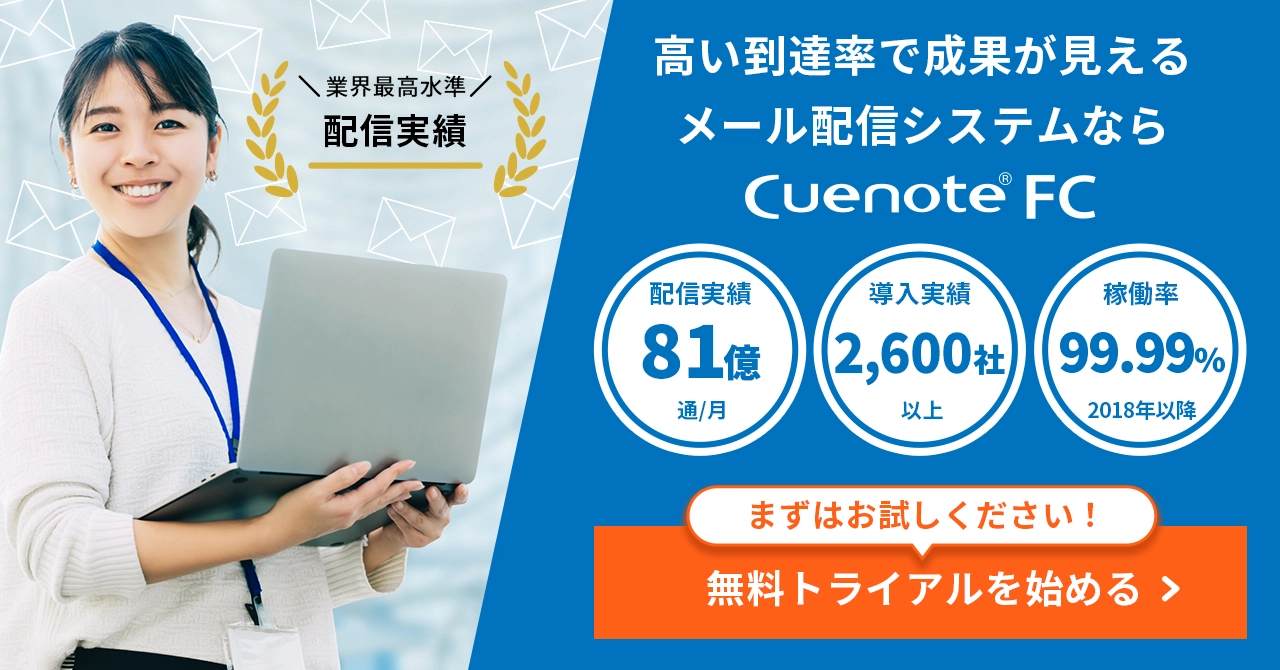ショートメッセージを予約送信する方法と活用方法を解説
ブランディングとは?目的や行うべき施策について詳しく解説

ビジネスではブランディングが大事。
マーケティングや営業・経営者などを中心にこんなフレーズを聞いたことはあるはずです。しかし、具体的にどうすればいいのか、そもそもブランディングとは何であるのか疑問に感じている方も多いと思います。
そこで当記事は、ブランディングについて解説したのち、ブランディングでの具体的な施策について紹介していきます。
メールマーケティングを
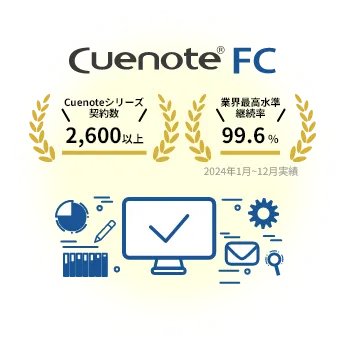
Cuenote FCはハイスピードな大量配信を得意としながら、効果測定や自動処理も可能で大手企業にも選ばれるメール配信システムです。メールマーケティング機能も豊富で、配信数上限はなく送り放題です!
ブランディングとは?
ブランディングとは、会社や商品・サービスに対して顧客が抱くイメージ・ブランドイメージを構築する活動を指します。
例えば、日本という国で考えてみましょう。世界から見れば、独自のカルチャーであるアニメや寿司などの日本食、そして治安の良さなどをイメージするでしょう。近年の韓国に対しては韓流ドラマやK-POPのイメージを強く持つ方も多いはずです。
継続的なブランディング活動を通じて、人々の心の中にイメージが徐々に構築されていきます。
ブランドの語源は焼印
ブランド(brand)の語源は、家畜に対して所有者が分かるように示す押す焼印です。そこから、商人たちが自社の商品を識別するために印やマークを付け始めました。印があることによって商品の品質を示すことができました。現代の私たちが「ロゴ」や「社名」と聞いてイメージする「ブランド」も、元をたどればこの「印」から始まったと言えるでしょう。
そして物理的な「印」という概念から、「企業や商品の持つ固有の価値、魅力、顧客の信頼」といった、より抽象的な意味合いの「ブランド」へと発展していきました。
ブランドには「アイデンティティ」と「エクイティ」などがある
ブランド戦略を円滑に進める上で、「ブランドアイデンティティ(Brand Identity)」と「ブランドエクイティ(Brand Equity)」は特に重要な概念です。
ブランドアイデンティティとは、企業が自社のブランドに対して「顧客にどのように認識され、どのような価値を感じてもらいたいか」を明確に定義し、意図的に構築する理念や視覚的要素、メッセージなどを指します。
一方、ブランドエクイティとは、顧客がそのブランドから実際に受け取る認知度や品質への連想、信頼、忠誠心、そしてブランド資産(商標、特許など)の総和として、顧客のブランドに対する集合的な評価を指します。
ブランディングのマーケティングや広報・PRとの違いは?
ブランディングは、長期的に顧客が抱くイメージを構築するもので、直接的に売上を目指すものではありません。対してマーケティングは直接売上や問合せを目指す活動が主です。広報・PRは、その中間にあたり、認知を高める活動に当たります。
目的、ゴール、時間軸、成果指標(KPI)、自社への問いという5つの項目で、それぞれの違いは以下の通りです。
| 項目 | ブランディング | マーケティング | 広報・PR |
|---|---|---|---|
| 目的 | ブランドの価値・世界観を築き、認知・信頼・共感を得る | 商品・サービスを売るための市場創造と顧客獲得 | 社会・メディア・ステークホルダーとの良好な関係構築 |
| ゴール | 「このブランドが好き」「信頼できる」と感じてもらう | 売上・シェア・顧客数の増加 | ポジティブな企業イメージと信頼性の向上 |
| 時間軸 | 長期的 | 中〜短期的 | 中〜長期的 |
| 成果指標(KPI) | ブランド認知・ロイヤルティ・好感度 | 売上・リード数・コンバージョン率 | メディア露出量・報道数・SNS言及数 |
| 自社への問い | 「私たちはどんな存在でありたいか?」 | 「どうすれば売れるか?」 | 「どう見られたいか?どう信頼されるか?」 |
なぜ、ブランディングは重要なのか
ブランディングが重要な理由は、顧客から選ばれ、長期的な関係を築くことで、継続的で効率的な売上・利益を上げることに繋がるからです。主に以下3つのポイントに沿って詳しく解説していきます。
ニーズが高まった時の想起に繋がる
「掃除機と言えば」「スマートフォンと言えば」など、あるカテゴリを上げた時に浮かぶ商品群のことを「エボーグドセット(想起集合)」と呼び、人により想起する商品は変わります。売上を高めるためには、想起する人を増やすこと、そしてその確率や想起される順番を上げる必要があります。
ブランド力が強いとカテゴリ名より前に商品名が思い浮かぶケースもあります。例えば、スマートフォンの場合、先に「iPhone」をイメージするケースもあるのではないでしょうか。ブランディングはこのようにニーズが高まった時の想起に繋げることができます。
信頼度・好意度の高さは選ばれる確率が上がる
エボーグドセットに入り想起されても、実際に購入されるかどうかは分かりません。極端な例では「旅行先と言ったら」という質問を上げた時に良い旅行先だけではなく、嫌な思い出・自分の好みと違った旅行先を思い出すケースもあるでしょう。これらは選ばれることは、ほぼないでしょう。
エボーグドセットに入った中で選ばれるためには、商品・サービスに対する好意度や信頼度が高くなければならず、そのためにブランディングが重要になります。
過剰な広告や営業といった費用や工数などのコストが抑えられる
人は暑いとアイスを食べたくなることもあるでしょう。アイスと言ったら食べたくなる製品があれば、それは広告を見ずとも購入するのではないでしょうか。
強いブランド力は、過剰な広告費用や営業工数を削減する強力な手段です。例えば、ニーズが発生した際に「あの製品なら間違いない」「これを使いたい」と指名買いされるようなブランドは、多額の広告費を投じなくても顧客が自ら探しに来るでしょう。また、高い信頼性を持つブランドは、新規顧客獲得にかかるコストを抑え、既存顧客のリピート率向上にも繋がり、結果として長期的なコスト効率の改善に貢献します。
ブランディング活動を行うためのステップ
- ブランディングしたい対象を分析する
- 理想のブランド像を描く
- ブランドコンセプトを策定する
- ブランドアイデンティティ(ロゴ・トーンなど)を定義する
- 実際の施策に落とし込む
- 効果を測定し、改善を続ける
ブランディングしたい対象を分析する
会社なのか商品・サービス・人などブランディングしたい対象について、「今どうみられているのか」「どんな強み・弱みがあるのか」など、分析する必要があります。ここでは定量的な集計、フレームワークによる分析、そしてリアルな状況による分析の3つの視点で分析しましょう。
Webアンケート・調査での定量分析
Webアンケートは主に2パターンあります。
- 顧客に対してWebアンケートを取ってどこを評価しているのかを調査する
- モニター協力を得る市場調査で、自社の立ち位置を分析する
ブランドの立ち位置を理解する上では、まず顧客の声をしっかり聴くことが重要です。店舗においても二次元バーコードでアンケートを読み取ってもらい、回答者にはクーポンなどを配布することで協力してもらうことができます。満足度やその商品を誰かに勧めたいかなどのNPS(ネットプロモータースコア)や、なぜ購入したのか、利用しているのかなどの設問からヒントを得ることができます。
また市場調査では、「〇〇と言ったら?」のようにカテゴリ名を挙げた設問で、エボーグドセットにどの程度入っているか、また選ばれる率を調査することができます。また顧客ではない層に、イメージを聞くことで現時点でのブランドイメージを確認することもできます。
フレームワークを使って考える
- 3C分析:自社、競合、市場を把握し、自社しか満たせないニーズを把握
- SWOT分析:自社の強み弱み、機会や脅威を分析
- PEST分析:政治・経済・社会や技術の観点から、社会の変化から立ち位置を探る
上記のような代表的なフレームワークがあります。使い方のポイントとしては、社会の変化や自社の状況など、視点を漏らさずに確認することです。行うべき訴求を考えた後に、「競合が行っていた」「社会の変化に合わない」などの結果になってしまうことが無いように、考えていくことが大切です。
現場や顧客など直接接してヒアリングを行う
定量的な調査やフレームワークでは見えない、空気感など感覚的な面やリアルな1人の声は、自社の状況を理解する上で重要です。顧客に対して直接ヒアリングすることや、店舗など現場に直接出向きヒントを得ることは重要です。
理想のブランド像を描く
次に、顧客にどのように認識されたいか、どのような価値を提供したいかブランド像を描きます。ブランドが目指すべき方向性を考える上で重要なステップです。
ポイントは、ただ顧客の意見や市場に流されず「自社がどう思われたいか」を考えることです。売上を高めるブランディングを行うためには「ブルーオーシャン戦略」を取ることも重要です。
これは単純に目に見えたニーズや顧客を追うのではなく、隠れたインサイトや顧客になっていない層の課題を見つけ、今の商品・サービスが改善の余地も含めて、解決することができるのかを考えることも大切です。
ブランドコンセプトを策定する
このステップでは、顧客にイメージしてほしいブランドの価値を言語化します。言語化する際には、まず「誰に対して、どんな市場環境や課題・ニーズがあり、どんなことを提供しているのか」など視点・項目ごとに言語化していきます。
そして、一言で伝わるようなキャッチコピー化もしましょう。例えば、手軽に暖かい飲み物を飲みたい人に対して、最初に何ワットの電力により、何分で100度まで沸騰できる湯沸かし器など、スペックや詳細を入れた文章を考えます。その後、「1つのボタンで直ぐに沸かせる湯沸かし器」のようにキャッチコピー化を行います。
このように突然抽象度の上げた言語化では、業務をする上では認識に齟齬が出てしまうので、視点・項目ごとに言語化したのち、一般の人にも伝わるキャッチコピー化をする必要があります。
ブランドアイデンティティ(ロゴ・トーンなど)を定義する
伝えるべきブランドコンセプトが定まったら、各施策に落とし込むために「ロゴ」や「デザイン・実際に広告文などで記載する文章のトーン」を定義していきます。
前のステップでキャッチコピーを決めたとしても、掲載する場所・媒体によっては、文章での説明や図での説明など、伝えるべき内容が変わります。そこで、方向性が変わらないようアイデンティティを定義する必要があります。レギュレーション・マニュアルを作成すると良いでしょう。
実際の施策に落とし込む
ブランドアイデンティティまで決まったら、それをどのように顧客に届けイメージの定着を図るかを考えていく必要があります。また、単にブランドアイデンティティを伝えるだけではなく、その企業・ブランドと顧客の関係性を構築していくことも重要です。例えば以下のような施策が考えられます。
- SNSを利用して直接接点を構築する
- 商品パッケージや広告文にブランドアイデンティティを入れる
- YouTubeやブログなどで、詳しく情報を伝えて深く理解してもらう
詳細は次の章にて解説していきます。
またブランディングに対しては、どのように訴求するかだけではいけません。商品・サービス自体をブランディングアイデンティティに合わせて強化していく必要があります。また、関わる従業員の1人1人の立ち振る舞い、考え方もアイデンティティを踏まえていく必要があります。
効果を測定し、改善を続ける
ブランディングでは効果を定量的に測定し、改善する必要があります。施策を行っただけで終わる「やりっぱなし」は、自己満足になってしまうことやブランドイメージが低下してしまった場合に早期に気付くことができないため危険です。
ステップ1と同じように「Webアンケートで顧客調査、市場調査」を行いましょう。満足度に変化が無いか。顧客のイメージ・エボークドセットの量に変化はないか定量データを元に比較します。合わせて定量的なデータの裏付けとなるよう、現場に出向いて定性的な状況の変化を知ることも重要です。
ブランディングで行う実践的な手法とは
ブランディングを行う上では、定期的な接点を持つことと、しっかり情報を伝えていくことが重要です。関連する手法について解説していきます。
SNS運用
SNS特にInstagramは、ショート動画や画像を中心とした投稿により、世界観の表現に長けています。また、非常に多くの人が利用していることから、ブランディング施策としてオススメです。
例えば、小さなお子様連れでも大丈夫なホテルであれば、そのホテルで子供が楽しんでいる様子、子供と一緒に親が楽しんでいる様子。親が安心して子供を遊ばせている様子などを、動画や画像で表現することができます。メーカーであれば、利用者の様子だけでなく、開発秘話や製造過程での拘り、働く人の様子などを伝えることで信頼感の醸成に寄与できます。
SNSはそもそも広告など直接的な宣伝は適しておらず、このような投稿のほうが評価を得やすくなります。寄せられたコメントには返事をすることや、自社商品に対しての投稿を促すための投稿企画や、投稿しやすいようにハッシュタグを作成したり、サイトなどで活用する「UGC活用」することで、第三者の口コミによるブランディングも行えます。

SNSマーケティングとは?メリットや手法、成果を上げるポイントを解説
YouTube運用
「ブランディングの上でのYouTube運用」とは、単に動画を投稿して再生回数を増やすことではなく、ブランドの世界観・価値・信頼を構築・発信するためにYouTubeを戦略的に活用することを指します。
例えば調味料のメーカーであれば、料理のレシピをショート動画よりも深く紹介することなどもできます。また、開発秘話や働く人の様子も、10分以上にわたる動画で伝えることができます。ただし、視聴者にとって楽しめる動画でないと再生されないため、企画には工夫が必要です。
ブログなどのコンテンツマーケティング
ブランディングにおけるブログなどのコンテンツマーケティングは、企業や個人の「価値観」や「専門性」を継続的に発信し、信頼と共感を育てる手法です。単なる商品紹介ではなく、読者の課題解決や興味を引く情報を提供することで、ブランドの世界観やストーリーを伝えます。
たとえば、アウトドアブランドが登山ノウハウや自然保護活動の記事を発信することで、「自然と共に生きるブランド」というイメージを強化できます。このように、継続的な有益コンテンツの発信は、検索流入による認知拡大とともに、ブランドへの信頼とファン形成を促進します。
生成AIの登場により、ブログはSEO対策としての集客力の側面ではやや低下傾向ではありますが、コンテンツそのものは生成AIの学習元にもなり、今後も重要です。
メールマーケティング
メールは、SNSと異なりプラットフォーマーがいないため、アルゴリズムなどの影響を受けません。顧客に対して直接情報を届けられる稀有な手段の一つです。そんなメールを活用したマーケティング手法の代表である「メルマガ」は顧客と定期的な接点を構築できるため、ブランドに対する好意度や信頼感を高めることができます。
メルマガと言えば広告色の強いメールを送るイメージもあると思いますが、ノウハウの提供など有益性を上げることでブランディング向上の効果も十分期待できます。

メールマーケティングとは?基礎やメリット、効果的な手法を最新調査から完全解説
さいごに
ブランディングは抽象的であり、イメージしにくい部分もあります。ざっくりまとめると「ターゲットに対して商品・サービスを認知してもらい、愛されること」です。フレームワークや理論などさまざまありますが、囚われ過ぎないことも重要です。
またメールマーケティングについては当社のメール配信システム「Cuenote FC」をぜひご利用ください。

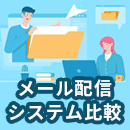 【2025年最新】メール配信システム比較17選!種類や機能・目的別選び方を徹底解説
【2025年最新】メール配信システム比較17選!種類や機能・目的別選び方を徹底解説
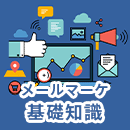 メールマーケティングとは?最新調査から基礎やメリット、効果的な手法を完全解説【2025年版】
メールマーケティングとは?最新調査から基礎やメリット、効果的な手法を完全解説【2025年版】
 メルマガは読まれない?購入や成果に繋がるメールコンテンツとは
メルマガは読まれない?購入や成果に繋がるメールコンテンツとは
 メールマーケティング・メルマガのKPI設定と運用・改善について
メールマーケティング・メルマガのKPI設定と運用・改善について
 メールでパーソナライズする方法とは?メリットも解説
メールでパーソナライズする方法とは?メリットも解説
 バイラルマーケティングとは?メリットや具体的な施策を解説
バイラルマーケティングとは?メリットや具体的な施策を解説
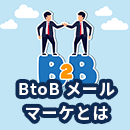 BtoBのメールマーケティングの効果と効果的な方法などを解説
BtoBのメールマーケティングの効果と効果的な方法などを解説
 セミナー集客を増やすメルマガのコツとは?効果的な件名も解説
セミナー集客を増やすメルマガのコツとは?効果的な件名も解説