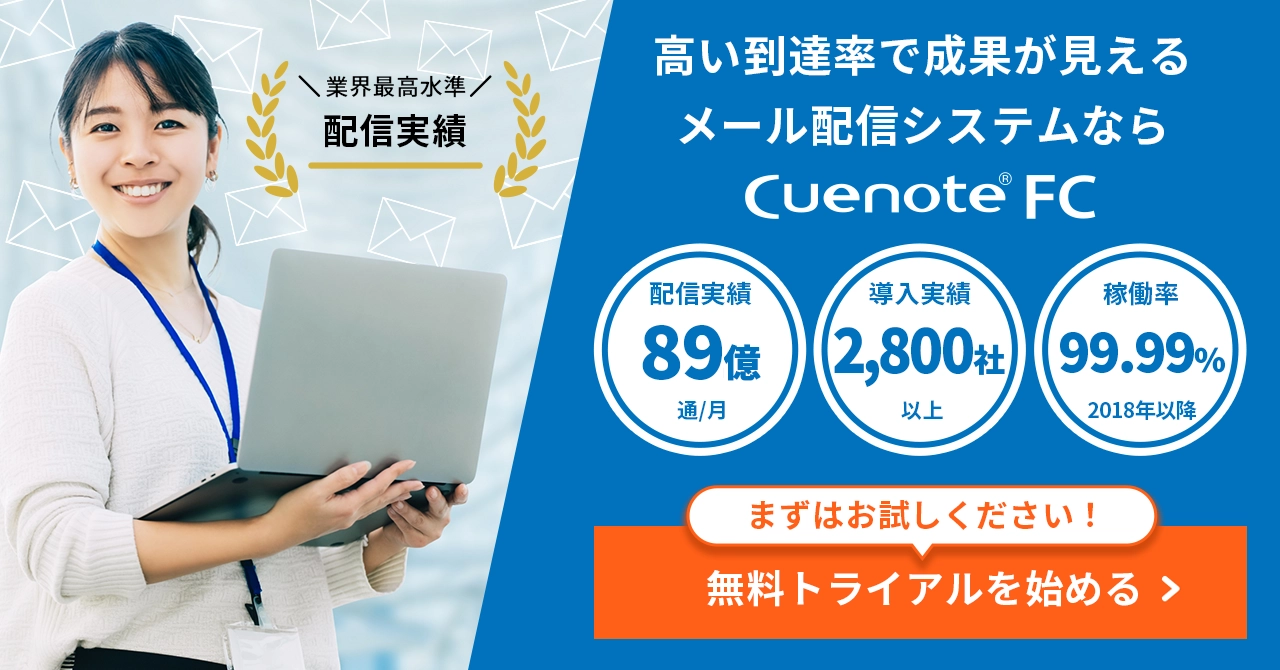メールが行き違いになった際の対処法は?原因や対策を解説
アンケートで精度の高い回答を集めるコツ5選

近年アンケートは、ツールの増加やIT技術の発展に伴い、誰でも気軽に収集することができるようになりました。しかし、ただ知りたい事だけを設問として設定してしまうと、回答が矛盾してしまうことや結果から得られるものが少なくなる可能性があります。
今回は、アンケートで精度の高い回答を得られるコツを分かりやすく解説していきます。
アンケートの目的を明確にする
アンケートを通じて何を知りたいのか、目的を明確にすることは非常に重要です。目的がぶれてしまうと「こんなことも聞きたい」など思い付きから設問が本題とズレてしまい、アンケート内容が散漫になることや結果を元にした分析もし辛くなります。
目的は「誰に対して、どういう調査をして、どのような疑問に対する回答を得るのか」など具体的にしましょう。またそもそも得られた回答をどのように活かす予定なのかも考えておくと良いでしょう。
アンケートの対象者を適切に絞る
例えば「今の自家用車の課題を見つけたい」という場合において、国内において免許を持つ可能性のない10代前半をターゲットにしても良い回答を得られる可能性は低いでしょう。
また20歳以上でも免許所持の有無や、現在自家用者を持っているかの違いによっても得られるアンケート結果は異なるでしょう。「自家用車を持っている人に対して課題を聞きたい」なのか「自家用車を持たない免許所持者に対して、どうすれば購入してもらえるのか」など、目的に沿った具体的なターゲットを設定するようにしましょう。
全体的な設問の流れや内容をロジカルにする
設問は、抽象的・全体的な内容から、具体的・部分的なものに移行するようにしましょう。例えば、「カレーは好きですか?」から「週何回カレーを食べますか?」に繋げるなど、順番に気を付けましょう。
また設問の内容によって、同じような質問を入れてしまうなど、回答結果を見た際に矛盾が生じてしまうことが無いように注意しましょう。
回答者が分からない、専門用語を使用しない
アンケートは、悩まず考えずに回答できることが重要です。回答者が分からないであろう専門用語を含んでいると、認識の齟齬が発生します。また回答に悩み中断されてしまう可能性もあります。
一方、回答者が分かり、専門用語を入れることで端的に伝えやすい場合には適切に使用したほうが良いでしょう。そのため、アンケートを作成する際にはどういう人が回答するのか、事前に確認しておいたほうが良いでしょう。
専門用語を使う場合においては、念のため補足などに説明や認識の齟齬がないように前提などの説明を記載するようにしましょう。
あいまいな表現を避ける
回答に悩むあいまいな表現は、回答されづらくなるだけでなく、回答結果を分析する際にも判断に迷う可能性があります。
例えば「あなたがよく飲むコーヒーは何ですか?」という質問。「よく」という単語の頻度は、人によって異なります。
例1)よく飲むコーヒーについて教えてください
→ 頻度を提示:週に3杯以上飲むコーヒーについて教えてください
例2)いつもお使いの携帯は何ですか?
→ 程度を指定:メインでご利用になっている携帯電話について教えてください
→ 最も使用頻度の高い携帯電話について教えてください
あいまいな表現になりがちな単語は概ね「形容詞」です。大きい・多い、重いなど、形容詞は人によって判断が変わります。例のように必ず数字を用いて、価値観などによる回答のブレを無くしましょう。
マトリックス利用時は回答する方向を補足する
アンケートでマトリックスを利用する時には注意が。必要です。
作成側からはつい見逃してしまいがちですが、意外と分かりづらさが出てしまうのがマトリックスの利用時です。回答者側にとっては慣れていない可能性があることも配慮しましょう。
左側の列に各項目の質問、右側で「良い/どちらともいえない/悪い」等の回答をするレイアウトが一般的ではあります。回答に迷う場合もあるため、補足例として「下に向かって回答を進めてください」等の説明があると親切です。
[自由回答欄では聞きたい範囲を絞り込んだ状態にする
アンケートの最後に配置されている事が多い自由回答欄。避けたい2つを例を紹介します。
1.「他の〇〇についてどう思いますか?」
回答できる範囲が広すぎると、回答者は迷ってしまい回答内容にブレが生じてしまったり、回答されない可能性があります。
例えば『今後の企画開発やサービス向上において参考にしたい』などの説明のうえで具体的に部分を限定・指定することで、より良いサービスに繋がる事を期待し、回答者側に真剣に回答してもらえる割合が増加します。
- 例1)〇〇カフェのサービスのなかで、良いと思う部分を教えてください
- 例2)△△カフェで一番好きなメニューを教えてください
2.「思いつくものを全て記載してください」
回答者に考えさせる設問は、回答にストレスを与えてしまいます。必要な場合は解答欄を3~5つなど、数を限定したうえで配置してください。
また、一つも思いつかないお客様も一定数いるケースもありますので、「思いつかないかたは枠内になしと記載ください」などの説明を加えておくなど配慮も必要です。
事前にダブルチェックやテストをする
アンケートは、再実施が非常に難しい性質があります。それゆえ、実施する前にダブルチェックを実施することや、テスト回答を行ってみるなど、事前確認を怠らないようにしましょう。
さいごに
「貴重な時間を使って回答してもらう」という姿勢でいる事は、アンケート作成側にとっては忘れがちな課題でもあります。また、その製品やサービスにおいて長年のファンであるなど、ポジティブな理由がなければ、アンケートに回答をすることは回答者にとって負担が大きいものです。
「今回ご紹介したコツはウェブアンケートでも、用紙のタイプのアンケートでも対応できる内容です。アンケートが作成できたら実施の前にぜひ一度、回答者側の視点になって見直してみてください。
![]() キューノート サーベイ
キューノート サーベイ
Cuenote(キューノート)のアンケートシステムは、直感的な操作画面で誰でも簡単にWebアンケートや問い合わせフォームを作成できるクラウド型(ASP・SaaS)サービス。PCの他、スマートフォンや携帯電話にも対応しています。
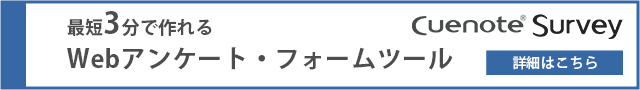
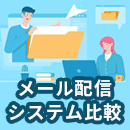 【2026年最新】メール配信システム比較17選!種類や機能・目的別選び方を徹底解説
【2026年最新】メール配信システム比較17選!種類や機能・目的別選び方を徹底解説
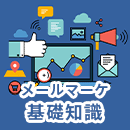 【2026年最新】メールマーケティングとは?基礎・KPI・効果最大化のコツを解説
【2026年最新】メールマーケティングとは?基礎・KPI・効果最大化のコツを解説
 【2026年最新】Webアンケートシステムとは?基礎知識と目的別の選び方を解説
【2026年最新】Webアンケートシステムとは?基礎知識と目的別の選び方を解説
 アンケートで選択式の設問は奥が深い。コツと基本設計を解説
アンケートで選択式の設問は奥が深い。コツと基本設計を解説
 アンケートの自由記述を効果的に活用するコツとは?分かりやすく解説
アンケートの自由記述を効果的に活用するコツとは?分かりやすく解説
 アンケートの成功には目的設定が重要!考え方を解説
アンケートの成功には目的設定が重要!考え方を解説
 アンケート結果を分析する方法を解説!より分かりやすく魅力的にするコツとは
アンケート結果を分析する方法を解説!より分かりやすく魅力的にするコツとは
 ウェビナーアンケート回答率を上げる12の方法を解説
ウェビナーアンケート回答率を上げる12の方法を解説