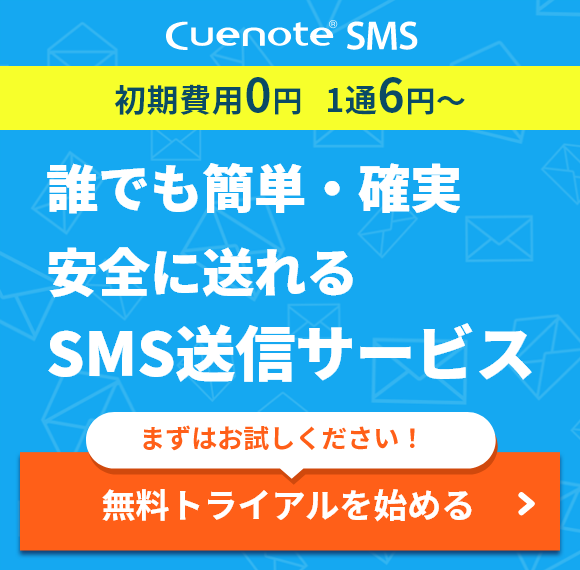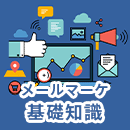メールが行き違いになった際の対処法は?原因や対策を解説
SMS送信にかかる費用は?料金体系を個人・法人に分けて解説!
関連製品:

SMS(ショートメッセージサービス)は、電話番号を用いて短いメッセージを送受信することができる便利なサービスです。個人間でのメッセージのやり取りや、本人認証の役割があるSMS認証・重要通知などのビジネス利用も一般的です。
そんな SMSを使うにあたって、料金・費用はどのくらいなのでしょうか?当記事では個人利用・法人利用それぞれの視点から紹介していきます。
成果が見えるSMS配信を

Cuenote SMSは1通6円からの業界最安水準の価格で、携帯電話の番号宛にメッセージを送信するSMS送信サービスです。専用ソフトは不要でPCや既存システムから簡単にSMSを送ることができ、ほぼ確実に読まれます!
SMS送信にかかる料金・費用は?
SMSは、受信は無料ですが、送信には料金がかかります。
送信料金は1通あたりの文字数や契約しているキャリア、利用する場所などの条件で変わってきます。また、「個人利用」と「法人利用」でも料金が変わってきます。
個人の場合は3円~33円
個人の携帯電話でSMSをやり取りする場合、送信料金は1通あたり約3〜33円前後です。 料金は、送信する文字数に比例して上がります。なお、同じキャリア同士や契約プランなどの条件によっては、料金がかからずに使用できる場合があります。電話が繋がらなかったり、要件を伝えにくかったりする場合には非常に有効な手段です。
実際の文字数ごとのキャリアのSMS送信料金について
2025年1月30日時点では、docomo、au(KDDI)、Softbank、楽天モバイルの4キャリアと、格安SIM (ahamo、LINEMO、UQmobile、Y!mobile)は、すべて同じ料金になっています。
| 送信文字数 | 1回あたりの料金(税込) |
|---|---|
| 1~70文字 | 3円(税込3.3円) |
| 71~134文字 | 6円(税込6.6円) |
| 135~201文字 | 9円(税込9.9円) |
| 202~268文字 | 12円(税込13.2円) |
| 269~335文字 | 15円(税込16.5円) |
| 336~402文字 | 18円(税込19.8円) |
| 403~469文字 | 21円(税込23.1円) |
| 470~536文字 | 24円(税込26.4円) |
| 537~603文字 | 27円(税込29.7円) |
| 604~670文字 | 30円(税込33円) |
70文字までが最安の3円(税込3.3円)でそれ以降は概ね67文字区切りで3円(税込3.3円)ずつ増えていきます。そして70文字と670文字程度では10倍差があります。
文字数が多い場合には、メールやSNSなど別のサービスとの使い分けや、詳しい内容はSMSに記載するリンク先に誘導するなどで、費用を抑えられる可能性があります。
また海外向けにSMSを送る「国際SMS」を利用する場合、概ね50円か100円から始まり最大1,000円程度かかります。
法人の場合は8円~18円が相場
法人が本人認証・通知・督促・プロモーションなどをSMSにて行う場合に使用するSMS送信サービスの費用は、1通送信あたり8~18円前後から送ることが可能です。
ただし、個人の送信と同じく、70文字以降は67文字単位で1通分の料金として課金されることが一般的です。例えば、1通送信あたりの料金が8円の場合で130文字のSMSを送る場合には、70文字分の1通+60文字分の1通として、2通分の16円がかかります。
またサービス導入の初期費用はかからないケースが多くなっています。 海外の回線を利用した送信は8円前後に抑えられますが、到達率が下がる可能性があります。
法人で利用する場合は、メッセージを確実に届けられることや、一斉配信できることがメリットになります。またSMSの到達率や開封率を確認し、届かないメッセージに対する対応を行うこともできます。 送付先情報の管理やAPI連携など機能が備わっていますので、法人が顧客など多数に送る場合は、基本的にSMS送信サービスを利用することをおすすめします。
SMS送信サービスのキャリア直通と海外回線の費用などの違いは?
SMS送信サービスには「キャリア直収」と「非直収」の2種類あります。
キャリア直収のSMS送信サービスは?
docomo、au(KDDI)、Softbank、楽天モバイルといった国内携帯キャリアと「直接接続したサービス」です。1通当たりの料金相場は「8円前後」です。以前までは「12円前後」が相場でしたが、近年値下がり傾向にあります。
「直接接続したSMS送信サービス」は国内携帯キャリアが正規ルートとして定めている国内回線からSMSを送信することができます。
国内の正規ルートを通して送信が可能なSMS送信サービスを利用する場合は、携帯キャリアからブロックされる割合が少なくなります。
そのため、国内の携帯キャリアにSMSを確実に届けたい場合は直収のSMS送信サービスを導入すると到達率の改善が大きく見込めるでしょう。
非直収のSMS送信サービス?
「非直収」のSMS送信サービスとは、国内携帯キャリアと直接接続しておらず、国際回線からSMSが送信されます。1通当たりの料金相場は「8円前後」です。
国内携帯キャリアが定めている正規ルートでのSMS送信ではないため、非直収のSMS送信サービスでは到達率が下がる懸念があります。
海外のSMS流通量は、ビジネス用途としても活用が定着しつつあり、日本と比較して圧倒的に多く、基本的に国際回線を介してSMSが送信されています。
海外ではSMSを利用してスパムメッセージを送信する悪用も多いことから、国内携帯キャリアは国際回線から送られるSMSを一定数ブロックする仕組みが働き到達率が下がってしまいます。
そもそもSMS送信サービスは?どんな特徴?
法人においても、1つの携帯を使いSMSを送信することはできますが、SMS送信サービスを使うことが一般的です。その特徴を紹介します。
SMSを一斉送信できる
SMS送信サービスでは、SMSを一斉に送ることができます。キャンペーン告知や広告配信など大量に複数の宛先に対して送るときに便利です。 電話番号しか取得できていない顧客に向けても送信ができ、メールと比較して確実に見てもらえる可能性が高くなります。
また個別の携帯電話ではなく主に管理画面から送るため、属人化を防ぐことや、セキュリティの観点からも法人がSMSを送る場合には、入れておいたほうが良いと言えます。
セグメント設定や、宛名を差し込んだSMS送信機能がある
csvで一括に取り込んだ顧客リストに、電話番号以外の個人情報や属性情報(※)が含まれていれば、SMS送信時に特定の属性をもつ人にだけセグメント抽出をしてSMS送信ができます。
また、宛名を差し込んだりすることができるため、よりメッセージの着眼率も高まります。
(※)属性情報の例:性別、地域、購入日時など
SMS送信後の結果を測定、分析できる
SMS送信サービスの管理画面上から配信した結果をリアルタイムに確認することができます。
例えば、重要な連絡(督促通知や請求通知、工事の日時確定)を確実にミスなく伝えたいシーンがあると思います。
SMS送信後の到達可否、詳細を明記したURLをきちんと確認してもらえたかなど、送信した対象を個人単位で確認することができます。
開封状況が分かるのでキャンペーン告知等の際には、開封されたか等の興味関心の効果測定にも活用ができます。
長文のSMS送信が可能
SMS送信は一般的に1通当たり70文字程度の文字数制限がありますが、SMS送信サービスの場合、600文字以上の長文SMSを送信できます。
SMS送信サービスの費用対効果は?
はがきDMとSMS送信の費用対効果の違い
料金面では、はがきは2024年10月から値上げがされており、1通当たり85円と旧料金の63円から値上げされています。
SMS送信では値下がり傾向があり、1通当たりの料金相場は8円程度ですが、送信数が増えるにつれボリュームディスカウントがあるケースもあり、1通6円から送ることができるサービスもあります。そのため、多くのケースでSMSのほうが安くなります。
費用対効果の面では、DMの場合は測定ができません。読まずに捨てられてしまう可能性があります。一方、SMS送信の実際に効果測定を行うことができます。また開封率は一般的に90%以上と言われており、確実性が高いツールと言えます。
なぜ開封率が高い?
開封率が高いと言われる理由は主に以下の3つあります。
- スマートフォン・携帯電話に標準搭載で誰でもすぐに利用できる
- ポップアップ画面に通知が届き見逃され辛い
- eメールと比べ、流通量が少なく埋もれ辛い
SMS送信とメール配信の費用対効果の違い
SMS送信とメールを費用対効果の面で比較した場合、開封率やリーチの高さなどだけみると圧倒的にSMS送信の方が効果は高いといえるでしょう。
ただし、SMS送信のデメリットとして1通送るごとに料金が発生してしまうので、配信コストを考えると圧倒的にメール配信のほうが安いといえます。
また基本的にSMSはテキストメッセージのみなので、メールのように画像を差し込んだり色を変えることができないのでシンプルなイメージでの訴求しかできません。
メールかSMS、どちらのツールを使うかを判断する際に重要なポイントが"用途や目的に応じて使い分ける"ことです。
SMS送信は下図のように「特定の用途」で利用されるケースが多いです。
SMSの活用シーンは多岐に渡ります
アプリやWebサービスの本人認証にSMSを活用
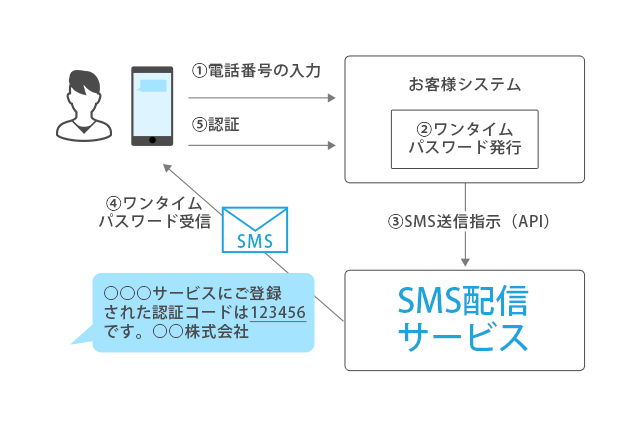
金融機関のWeb・アプリサービスやウォレット・送金機能を備えたアプリ、またアプリ内課金を行うゲームサービス等における、迅速かつ確実な本人認証にご利用できます。
メールアドレスのように複雑な文字列をユーザーに入力させる手間も省け、入力ミスも低減。
入金・決済・手続き期限の重要なリマインド
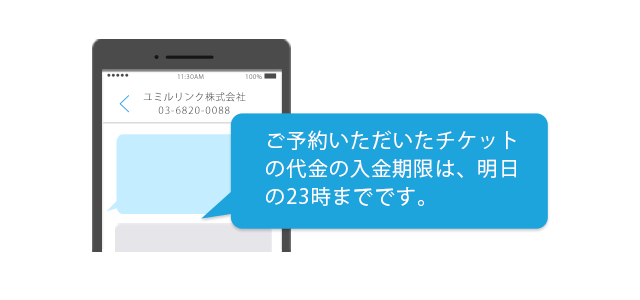
プレイガイド/EC/WEBサービス/金融機関 etc
Web上で購入した物品やサービスの入金や利用料引き落とし、また手続きの期限等のリマインドにSMSを活用。確実に届くので見落としも防げ、「うっかり!」によるロスも防げます。
携帯番号しか知らない従業員への
業務・緊急連絡ツールとして活用
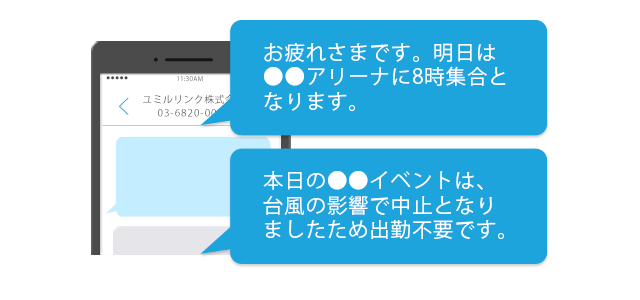
建設業/警備会社/派遣会社 etc
現場作業員の方や、派遣労働登録者向けの通知にも、確実に届くSMSが有効です。中止連絡など急を要する通知でも、いち早く届き着眼されます。
必ず確認してほしい予約・手配内容の通知
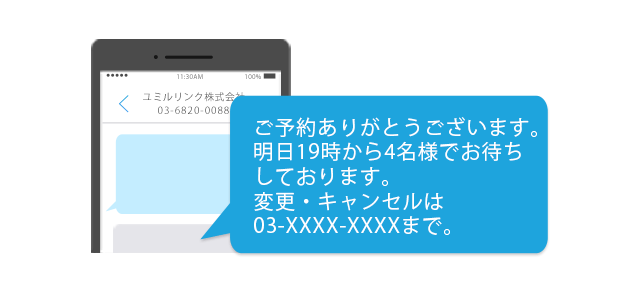
飲食店/サービス業/医療機関 etc
飲食店や美容室等、事前予約を受け付けつける事業者様や各種手配サービスなどの予約内容通知に。内容確認に加え、スケジュールの勘違いなどによる直前キャンセルの防止にも役立ちます。変更時の連絡先も併記すればスムーズな手続きを誘導できます。
コールセンターなど、利用後のアンケート収集
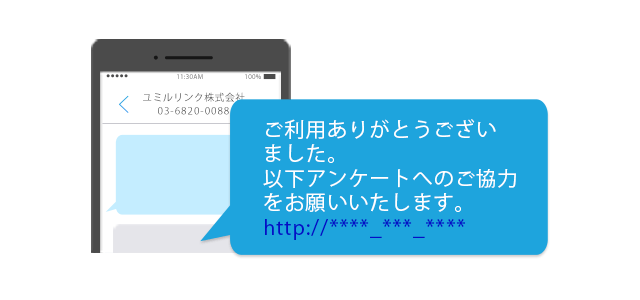
宿泊施設/小売店/その他サービス業 etc
お客様からの声をWebで集めて、顧客満足度の向上に繋げる施策もSMSなら確実に届いて回答率アップが期待できます(Webアンケートの実施は、WEBアンケートシステムを活用すると便利。
具体的な活用例として、アプリのインストールやログイン、チケット購入時のなりすましを防ぐ本人認証などをはじめ、督促、決済通知、業務連絡などの重要なメッセージを送る際に利用されることが多いです。
そのため、基本はメール配信で顧客にアプローチするが、確実に見て欲しい、もしくは緊急性の高いメッセージはSMS送信を活用するという、「用途に応じた使い分け」が有効的です。
ちなみにですが、今更メール配信?と思われたかもしれませんが、欧米で行われたポイントグラムの調査では35,000通のメール配信とDMの結果を比較すると、受け手の反応に大きな差はなかったものの、コストに関してはメール配信の方が100倍近く安かったというデータが出ていることからもメール配信が非常に費用対効果の高い手段だということがわかります。
コールセンターなどで人員・コスト削減の効果も
実は最近コールセンターやカスタマーサポートなどでSMS送信サービスの活用が増えてきています。
例えば、コンタクト担当者が電話対応中にお客様に確認をしてもらいたいURLを通話中の電話番号宛てに送信すれば、スマートな案内ができます。
通常、コンタクト担当者が顧客対応の電話を終えたあとに、顧客にメールや郵送物で案内を送るシーンが多くあります。この場合、コンタクト担当者が顧客一人への対応時間が長くなることに加えて、顧客が案内を待つ時間が発生します
これらの顧客対応が完了するまでの時間は、電話番号を利用したSMS送信で短縮できるため、スタッフがメールアドレスや郵送先の住所を確認・入力する手間も省けるといったメリットがあります。お客様側もすぐに案内を受けとれるので、確認漏れや待ち時間を減らすことができます。
上記の例のように、コンタクト対応の人員にあてる費用削減の効果も期待でき、SMS送信サービスの利用で1通あたり料金が発生したとしても、一定の費用対効果を期待することができます。
SMS送信サービスの料金と到達率面以外に大切な判断軸
料金も大事ですが、SMS送信サービスの機能面もチェックしておくとよいです。
自社に必要のない機能まで揃っていて、オーバースペックで不必要に料金が高くなってしまっているケースも少なくないため、あらかじめ要件を整理しておきましょう。
セキュリティ対策
セキュリティ対策の内容や要件はWebサイトや製品資料からだけではなかなか判断がつかないものです。
最も簡単な判断指標はSMS送信サービスの導入実績です。大手・上場企業や金融関係などはシステムを導入する際に厳しいセキュリティ要件を設定しているケースが少なくないため、SMS送信サービス事業者の導入先の企業をチェックしてみると分かり易いです。
サポート体制
何かトラブルがあった際に、すぐに対応してくれる体制が整っているか?
万が一、トラブルが発生したときにすぐに対応してくれる窓口があると安心ですよね。
eメールの問い合わせだけではなく、電話でのサポート対応はあるか?など、いざというときに質問しても対応を受け付けられる充実なサポート体制があるのかどうかも確認しておくと安心です。
SMS送信サービス選びで失敗しないためにも単純な1通あたりのSMS送信料金だけに目を向けるのではなく、しっかりと送信サービス事業者の体制も確認することをおすすめいたします。
SMS関連の資料ダウンロード
![]() キューノート エスエムエス
キューノート エスエムエス
SMS(ショートメッセージサービス)送信サービス、Cuenote SMS(キューノート SMS)は、インストールは不要で、携帯・スマートフォンを持っているユーザー全てに携帯電話網を利用したSMS送信が高速・確実に行えるASP/SaaSサービスです。開封率は90%以上という圧倒的な開封率の高さと、電話番号宛にメッセージを送れる利便性の高さが強みです。国内最高水準のメッセージングソリューションを手掛けるユミルリンクが培った配信技術と高次のセキュリティで、本人確認(SMS認証)や申し込みなどの通知をはじめ、決済通知、督促連絡、業務連絡、プロモーション用途等、様々な用途でのSMS活用をサポートいたします。

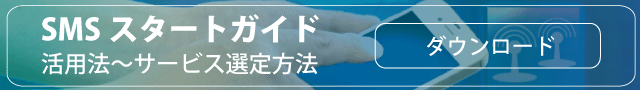
 【2026年最新トレンド】SMS送信サービス比較13選!選び方や比較ポイントについてわかりやすく解説
【2026年最新トレンド】SMS送信サービス比較13選!選び方や比較ポイントについてわかりやすく解説
 SMS認証とは?仕組みやメリット・導入方法やリスクまで完全解説
SMS認証とは?仕組みやメリット・導入方法やリスクまで完全解説
 iMessageの料金は?ビジネスで利用するなら知っておきたい注意点!
iMessageの料金は?ビジネスで利用するなら知っておきたい注意点!
 ショートメールがビジネスで大活躍!メリットや具体的な活用事例を解説
ショートメールがビジネスで大活躍!メリットや具体的な活用事例を解説
 SMSが届かない・送れない原因とは?送信者側・受信者側の対策を徹底解説!
SMSが届かない・送れない原因とは?送信者側・受信者側の対策を徹底解説!
 MMSとは?SMSとの違いや特徴、料金を比較しながら解説!
MMSとは?SMSとの違いや特徴、料金を比較しながら解説!
 SMSとは?メリット・デメリットやメールとの違い、ビジネスでの効果的な使い方も解説
SMSとは?メリット・デメリットやメールとの違い、ビジネスでの効果的な使い方も解説
 SMS認証(認証コード)が届かない?原因と解決策をご紹介!
SMS認証(認証コード)が届かない?原因と解決策をご紹介!